- それは、54戦隊がミサイルの第12斉射を行った直後に探知された。
- 「新たな熱源体、多数。右舷2時方向」
- ポートダーウィンのオペレーターが、目ざとくその一群に気がついた。決して彼が無能ではない証拠だ。「我隊を指向しているものと見られます」
- 「敵の種別と数を知らせ!」
- ポートダーウィン艦長、ブッパナス中佐は威厳をもって直ちに下令した。
- 「熱量とスピードからガトルを中心とする攻撃隊と思われます、モビルスーツの存在は不明。数は30以上」
- 「艦外カメラ、最大望遠、機関最大戦速、旗艦を援護する。ミサイルの斉射は続行せよ!」
- それは、本隊の直衛という地味な任務を命じられた、少なくともブッパナス中佐にはそうとしか思えなかった、中佐にとってはまたとない機会だった。くそ面白くもない任務なのだ、艦隊の直衛などというのは。艦隊砲撃戦、それこそがブッパナスの求める戦いだった。しかし、戦いの種類がたとえガトルの迎撃戦であれ、自分自身が危険にさらされるということは、快感以外の何ものでもなかった。
- 「メガ粒子砲、1番2番4番5番、右砲戦用意!!各機銃座、近接する敵は、1機も撃ち漏らすなっ!!」
- ブッパナスに心地よい加速感を与えながら加速するポートダーウィンの艦上で右側を狙える火器が、ゆっくりと右を指向する。
- 「各メガ粒子砲、射撃準備完了しましたっ」
- 副長から報告が上がるやいなや、ブッパナス中佐は、威厳に満ちた声で命令した。
- 「撃ち方始めッ!!」
-
-
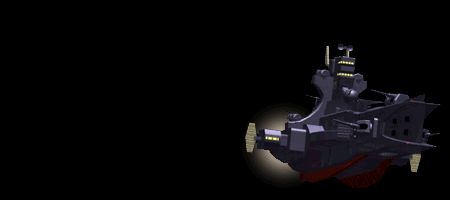
|
|
右舷に斉射を行なうサラミス級巡洋艦『ポートダーウィン』
|
- メガ粒子の、淡いピンクの光の線が、まだ視認できない熱源体に向かって伸びていく。各砲塔は、1分間に20斉射できる新型のメガ粒子砲の威力をまだ見ぬ敵に対して遺憾なく発揮していく。その両側を、統制の取れた動きでオタワのモビルスーツ隊が、迎撃のために同じようにまだ見ぬ敵へと突進を開始していた。思ったより早いその初動にブッパナスは、思わず感嘆を漏らしていた。
- (ほほぉ、お手並み拝見といこうか?)
- 急速に主戦力となりつつあるモビルスーツだったが、ブッパナスは、モビルスーツだけで敵を完全に阻止できるとは、これっぽっちも思ってはいなかった。絶対という言葉は、戦場にはないのだ。
- 「メガ粒子砲、あと3分で射撃止め。各機銃座、モビルスーツ隊をすり抜けてきたやつ、撃ち漏らすなよ!!」
- ブッパナス中佐は、この瞬間、確かに戦争を楽しんでいた。
-
- 「たどりつけませんよ、中尉」
- サブパイロットのブレン曹長が、泣きを入れる。
- 確かに、ア・バオア・クー空域全体が、双方の放つミサイルやビームで満たされて、1マイルだって無傷で進むことは不可能のように思える。それどころか、部隊の大半が、いまだに撃破されていないことのほうが不思議なくらいだ。その上に、メガ粒子砲の一斉射撃を受けているのだ。
- 脆弱なガトルは、たった1発の機銃弾でさえ致命傷となる、ましてやメガ粒子の直撃を受けたら・・・瞬時にあの世生きだ。
- 「あたりはしないと信じろっ!!」
- ハリソンは、前方を見据えながら言い放った。実際は味方の放った攻撃に撃破される可能性だってあるのだ。しかし、出撃した以上恐れをなして引くわけにはいかない。メガ粒子砲は、狙撃してきているわけではないのだ。
- それでも、運悪くメガ粒子砲に直撃されてしまう機体が皆無で済みはしなかった。5分にも満たない斉射で2機のガトルが、メガ粒子の火線に直撃され、一瞬で四散した。飛び散るガトルの破片が、ハリソンのガトルの外壁をノックしていく、許容を越えるような破片がもしも命中すればハリソンのガトルも巻き添えを食ってしまうが、そうはならなかった。しかし、爆発する僚機を避けようとする若いガトルのパイロットたちのせいで編隊は瓦解しようとしていた。
- 「各機、コースそのまま、編隊を崩すと各個撃破されるっ!!」
- 撃破された1機は、大隊指揮官のマーカス大尉のガトルだった。そのことが、余計に編隊の瓦解を促そうとしているのだ。ハリソンは、先任が自分だと知ると直ちに命令を下した。ハリソンの一喝で、瓦解しかけた編隊は、多少ばらつきはしたが決定的な瓦解にはいたらなかった。ハリソンは、部隊の中でも最も信頼を受けている人物の一人なのだ。
-
- フクタ少尉は、はなっから女のけつにつく、などというつもりはまったくなかった。接近するジオン軍の迎撃部隊の接近を知らされるや否や、真っ先にその先鋒を取った。自然と、小隊単位の突撃となり、フクタ小隊は、メガ粒子砲斉射の右、ゲリン小隊は左を進撃することになった。ボール隊は、4機と3機に分かれてもたもたと後方をついてきている。
- (馬鹿正直な・・・)
- フクタ少尉は、後方を映し出しているモニターに一瞥をくれながら詰った。ボールは、後方に控えていればいいのだ。馬鹿正直に、一緒になって敵を迎撃する必要はないはずなのだ。
- その瞬間、メガ粒子砲の斉射がやむ。結局2機しか墜とすことはできなかった。あれだけ圧倒的な火力であるにもかかわらず、やはり小型高速移動目標には艦載メガ粒子砲は、無力なのだ。
- まず、視界に入ってきたのは、ジッコだった。視界に入ってきた次の瞬間には、ミサイルをぶっ放してきた。しかし、ジッコのミサイルは、機体の真正面にしか指向できない。もちろん、無誘導だ。つまり、ほんの少し射線をはずせば、ジッコはジムにとっては無害な存在だった。そして、ジムはそれが簡単に実行できた。フクタ少尉にとってそれは児戯にも等しい。フクタ少尉は、軽くジムを機動させジッコの射線からいとも簡単に逃れると、ろくな回避もしないジッコにビームを放った。たちまち1機のジッコが、爆発する、さらに1機。あっさり2機のジッコを撃破したフクタ少尉は、しかし、今からが本当の戦闘だと言う事を知っていた。正面モニターには、ガトルを援護するザクが複数映し出されていた。
-
- ゲリンは、ジッコを攻撃しなかった。何故ならコーンウェル准尉とナガレ准尉に任せてしまえばいい相手だからだ。ゲリンのジムが装備するビームライフルは、威力こそ他のジムが装備するスプレーガンをはるかに凌駕するものの発射回数は限られている。ジムにとっても、艦隊にとってもそれほど脅威にならない相手に対し、無駄に使う性格の火器ではないのだ。
- フクタ小隊が3機、ゲリン小隊が2機のジッコを撃破し、突破に成功したジッコは、結局のところ1機でしかなかった。1機のジッコでは、どれほどのこともできるわけがなかった。事実、そのジッコは、ボール隊を突破できたにもかかわらずポートダーウィンの機銃座の斉射に取り込まれて無為に消えた。
- ゲリンのジムが、ライフルを使うべき相手は、ジッコの後ろにこそいた。6機のザクである。しかし、その機体は、よほど戦力が不足しているのか、ほとんどが、旧式の05タイプだった。だからといってゲリンは、決して相手を侮ったりはしなかった。
- 「ジム、06、07援護を頼む!!」
- ゲリンは、ジムを、最大加速させた。カスタムタイプのゲリンのジムが行う機動についてこられるジムは、ない。もちろん、ジオンのザクもだ。
- おびえるようなザクを見据え、ゲリンはビームライフルを照準した。
-
- 「この野郎、この野郎、このぉ〜〜〜!!」
- チュリル伍長は、目の前に急接近してくる連邦軍のモビルスーツに、ザクの105ミリマシンガンを向け、罵声とともに、発射した。旧式の火器だが、命中すれば損害の1つや2つは与えられる威力を十分に持つ。
- 連邦のパイロットが自分と同じ女性だとは、欠片も思いはしていない。
- 「墜ちないか、墜ちろ、墜ちろっ!!」
- 懸命に射撃し、言葉に力があるならとっくに撃墜できているはずなのに、その連邦軍のモビルスーツは、巧みな機動でまったく無傷のまま接近してくる。その刹那、ビーム、シャープで殺気立ったピンクのビームが放たれた。
- チュリル伍長は、思わず首をすくめ、射撃を止めてしまった。目を閉じなかったことだけは誉めてしかるべきだった。命中する!!その瞬間、2条のビームは、チュリルのザクの左右へ均等に分かれていった。思わず、後方視認カメラ用のモニターに遠ざかっていくビームを確認する。
- (よけられた?)
- おかしな話だったチュリルは、何の回避機動もしてはいないのだ。けれど、興奮しているチュリルは、自分で回避したように思えたのだ。
- 視線を前に戻した時、新たなビームが、機体に迫りつつあった。今度も、当たらない。チュリルは、そう思ったのだけれど、その結果がどうなったかを知ることは、チュリルにはできなかった。
- そう、チュリルは、ビームの中でその若い命を散らしてしまったのだ。
-
- 「伍長〜っ!」
- シュタイナー少尉は、思わず叫んだ。自分の斜め前を機動していたチュリル伍長のザクが、たったの3斉射で撃破されたからだ。
- チュリル伍長を撃破した敵に対して、少尉は教本通りのバースト射撃を送り込んだが、あっさりと躱される。
- その報復に送り返されてきたビームは、きっちりと命中し、シュタイナーに絶叫を上げさせた。しかし、その絶叫はいくらも続かなかった。ナカイ伍長が、撃墜されるのは、ついでのようなことだった。
-
- 敵の回避まで読んだ必殺の2撃は、敵が微動だにしなかったことで無駄弾丸になってしまった。ビームライフルの攻撃に驚いたのか、射撃をも忘れたその旧式なザクに、ゲリンは、今度は、真正面から一撃を加えた。それで終わりだった。あっけないほど簡単にそのザクは、ビームに貫かれ、一つの光芒にと変わっていく。
- もう1機のザクが、ゲリンを阻止しようと機動し射撃を送り込んできたが、そのザクもゲリンの1撃を全くなすすべもなく受けて、同じ道をたどる。そのころには、後方から追いついてきた准尉たちのビームスプレーガンの乱射で残ったザクも、あっさりと撃墜されていた。
- そのままガトルに向かおうとする准尉たちに、ゲリンは、叱咤する。
- 「ガトルは、いい、フクタ少尉を援護する」
- そのときには、もう、すでに1機のガトルを餌食にしていたが、素直に准尉たちはゲリンに従った。
- 確かに、ガトルを迎撃することも任務のうちだったけれど、フクタ小隊が、苦戦している今、ガトルは、ボール隊に任せてしまえばいい相手だった。
-
- 「くそったれっ!!」
- かろうじてザクの攻撃をシールドでかわしながら、フクタ少尉は、自分が貧乏くじを引いたことに気がついた。相手は、ベテランだった。シールドを通して伝わってくる激しい衝撃に戦意を失いそうになりながらもフクタ少尉は、必死で反撃を加えていた。
- しかし、こっちのほうが1機多いのにもかかわらず、全くイニシアチブが取れないのだ。思うそばから、識別信号が、1つ消える。遅れて、右後方から圧倒的な光が流れ込んでくる。
- 「や、やられたのか?」
- それは、紛れもない味方機の喪失の瞬間だった。
-
- 反動を吸収するとはいっても、120ミリもの大口径マシンガンの射撃の衝撃が全く伝わってこないなどということはない。リズミカルな衝撃は、必ず伝わってくるものだ。それをこまやかなバーニア捌きでコントロールし、射線のぶれを最小限に抑えつつ、連邦軍の人型に30発以上もの120ミリ弾を打ち込む。
- もちろん、30発全てが命中するわけもないが、少なくとも10発は直撃させた自信が、ブラドーにはあった。
- 「連邦軍の人型を墜としたければ、ドラム弾倉を空にするつもりで打ち込め!」とは、連邦軍のモビルスーツ隊と交戦したパイロットたちの口癖である。何発目が、致命傷になったかは別として、ブラドーは、初めて連邦軍のモビルスーツを撃破した。しかし、そこには何の感慨もない。
- この結果は、自分のようなベテランが、どじな連邦パイロットを相手にして初めて可能になったことが、わかっているからだ。それが証拠に、がんがん打ち出されるビームのせいで、サイクス曹長ののザクは、射撃を満足に行うこともできてはいない。クチン曹長が、なんとか1機を牽制している。学徒兵たちのザクは、瞬く間に3機をほぼ一瞬で撃破されてしまった。
- それを成し遂げた連邦軍の人型は、こちらを指向しつつある。
- ガトルは、無視している。
- (いい判断をするパイロットだ、手強い)
- てんでなっていないビームの攻撃を回避しながら、挟撃される自分たちが後どれほどこの連邦軍の人型をひきつけられるのか?ブラドーは、全く自信が持てなかった。
-
- (チュリルがやられたのか?)
- ブラドー中尉の、右方向から新たな敵が接近する、という、短い警告を聞いた瞬間、サイクス曹長は、頭に血が上ってしまった。まだ、間合いがあるにもかかわらず、サイクス曹長は、チュリルを撃破してなお、この戦闘空域に殴りこもうとする新たな敵に機体を振り向けた。
- しかし、感情に任せたその機動は、致命的なミスだった。正面の敵を撃破したわけではないのだから。
- そして、連邦軍は、そういったミスを見逃さなかった。
-
- 後退機動をしながら体勢を立て直したフクタ少尉のモニターには、側面を見せたザクがプロットされていた。近接してはいないが、ビーム兵器にとっては届かない距離でもない。61式時代のいい癖、照準した敵にはただちに発砲する、後のことはそれからでいい、がでた。フクタ少尉は、スプレーガンを、不用意に側面を見せたザクに向けて連続発射した。
- 発射間隔の短いスプレーガンは、ザクの機動をほとんど許さずに殺到した。
- ザクが、硬直したような動作を見せた後、そこに極小の太陽が出現した。モニターに、防眩フィルターがかかり、フクタ少尉の目を保護する。
- 「やっと1機か・・・」
- 回避運動を続けながら、フクタ少尉は、モビルスーツ戦が戦車戦よりもよほど繊細なことを思い知らされた。それに、ジムは、1人で全てをやらねばならないのだ。
-
- (突破できない)
- ザクが、連邦軍の人型をその全滅と引き換えにひきつけてくれているにもかかわらず、ハリソン中尉は、絶望感を味わいつつあった。
- 人型を突破してもなお、できそこないが防衛ラインを張っているのだ。できそこないとはいっても、もはや標的に向かって直線軌道を取らざるをえない学徒兵達にとって、自由自在な機動ができるできそこないは、恐ろしい相手だった。
- 21機で出撃してきたガトルも、もう7機を撃破されてしまっている。できそこないを突破してなお、敵の防空火器を潜らねばならないのだ。かろうじて生き残っているたった14機のガトルにとってそれは、不可能に近い仕事だった。
-
- 「もういけません」
- 指向性の強い無線を通して、3番機のメイソン中尉の声が聞こえてきた。「右のアームをやられてしまったので、自在な動きもできません」
- 「いったん、空域を・・・」
- 空域を離脱する、といいかけた第177特別機動小隊指揮官のランサム大尉の目に、右手前方で展開されつつある戦闘が、飛び込んできた。圧倒的な劣勢下で絶望的な突撃を敢行するガトル隊である。護衛のザクが、次々に撃破されている。
- もっとも、その状況は、ランサム大尉指揮下のビグロ隊にしても同じことだった。
- 圧倒的な火力、モビルスーツと同等の機動性、空間戦闘機を凌駕する高速性能、そういったうたい文句で正式化されたビグロの先行量産型4機と、宝石よりも貴重な各部隊から選抜されたベテランモビルスーツパイロットによって編成されたビグロ隊は、たった一度の突入で戦力を半減させられていた。
- いかに、技術士官や、高級将校が自信を持っていても、自分たちは、わずか3日でこの新しい機体を乗りこなせるほど、器用ではなかったのだ。
- それに、前方に固定されたメガ粒子砲は、ビグロの機動性を損なうには十分だった。
- もちろん、有力な兵器には違いない。小隊は、サラミスを1隻地獄に叩き込み、さらに1隻を大破させた。人型も5機は撃破したろう。できそこないは、端から相手にしなかった。
- しかし、いかに有力な兵器といっても場当たり的に投入されたのでは、有効でありえない。技術仕官のいう、一個戦隊を瞬く間に撃破することができるでしょう、といううたい文句とは裏腹に、その半分の戦果もあげることができず、2機のビグロをたった一回の突入で失ったのだ。そして、残ったビグロも、ランサム大尉のビグロも含め、機体のあちこちに損傷を受けてしまっている。
- もうろくな戦闘はできそうになかったが、目の前で壊滅しかかっているガトルの助太刀ぐらいはできそうだった。
- 「メイソン中尉、2時の方向のガトル隊を援護するぞ!」
-
- 突っ込んでくるガトルを、弾幕防御で阻止するだけでいい。苦手なザクは、ジムによって排除されつつある。いかに命中精度が高くないボールのキャノン砲でも、ほとんど回避もせずに突っ込んでくるガトルを餌食にすることは、動作もないことだった。
- 「撃ち方始め!!」
- オードリー曹長は、指揮下のボール隊に射撃を命じた。7機のボールが、各個に射撃を始めた。
- オードリー曹長も負けじと撃ちまくる。
- たちまち、1機のガトルが直撃を受け盛大な爆発とともに破片を飛び散らす、続けてもう1機が、吹き飛ぶ。さらに1機が直撃の影響だろうか?あらぬ方向へと突入方向を変える。
- (楽な戦闘だ)
- そうオードリー曹長が思ったとたん破局はやってきた。
- 「て、敵だぁ」
 左翼隊のリーゲン曹長の叫び声と同時に、火球が2個膨れ上がる。ボールの鈍いセンサーが、敵を捕らえたときには、オードリー小隊にもその新たな戦闘の参加者が襲い掛かった。戦艦から発射されるほどもあろうかというメガ粒子が、オードリー小隊に襲い掛かる。回避するまもなく、2機がビームに取り込まれる、そして、溶解、爆発。至近を通過する哨戒艇ほどもあろうかというジオン軍の新型兵器。振り上げたアームに叩き潰されてもう1機がパイロットごとへしゃげたのは、ついでのことだった。 左翼隊のリーゲン曹長の叫び声と同時に、火球が2個膨れ上がる。ボールの鈍いセンサーが、敵を捕らえたときには、オードリー小隊にもその新たな戦闘の参加者が襲い掛かった。戦艦から発射されるほどもあろうかというメガ粒子が、オードリー小隊に襲い掛かる。回避するまもなく、2機がビームに取り込まれる、そして、溶解、爆発。至近を通過する哨戒艇ほどもあろうかというジオン軍の新型兵器。振り上げたアームに叩き潰されてもう1機がパイロットごとへしゃげたのは、ついでのことだった。- たった1航過で、いかに貧弱なボールといえども5機を撃破するとは尋常な相手ではなかった。
- 右から左への航過にあわせて、慌ててボールを旋回させたオードリー曹長が見たものは、大きな機体に似合わない俊敏な敵の回頭性能だった。ボールが90度回頭し終わらないうちに180度回頭をし終えた大型の新型機のとがった機首が、鳥の嘴のようにくわっと開く瞬間が、オードリー曹長の見た最後の光景だった。
-
- ガトルに集中しているできそこないを撃ち落すのは、標的を射抜くようなものだった。2機をビームの餌食にしさらに1機をアームで殴りつける。メイソン中尉も、同じようにメガ粒子砲で2機を仕留める。航過したと見せて、アームを使った急速回頭をする。すさまじいGが襲い掛かるが、かろうじてそれを耐Gスーツと、鍛えられた体が、ランサム大尉を失神することから守ってくれる。回頭し、急制動をかけてビームの照準をつけたとき、できそこないは抵抗のそぶり、砲塔をこちらに向けようとした、を見せていた。しかし、その機動が完成するよりもたっぷり1秒は早く、ランサム大尉は、ビームを放った。
- 大口径のビームに、飲み込まれるように取り込まれたできそこないは、一瞬膨張し、火球に転じた。
- (もう1機)
- しかし、その思いは、予想より早くザクを一掃して駆けつけてきた連邦軍の人型によって叶うことはなかった。
- 「大尉、連邦軍の人型です!!」
- 「よし、そっちを片付けるぞ。続け!!」
- 「了解!」
- できそこないを殲滅し損ねたことは、残念だったが、ガトルは、突破できたのだ。もうガトルを邪魔するものは、いない。旧世代の兵器がどんな活躍を見せてくれるのか?見届けてみたいと思うが、それが叶わない事もランサム大尉は、知っていた。
-
- ゲリン小隊に、側方を衝かれた3機のザクは、あっさりと壊滅した。
- ゲリンが1機、コーンウェル准尉が1機、それにフクタ小隊の誰かが1機撃墜した。ザク隊にとってはそれはまさに悲劇だった。しかし、そのとき、別な悲劇が完了しようとしていた。小型の哨戒艇ほどもあろうかというジオン軍の新型機が、あっという間にボール隊を殲滅してしまったのだ。三角形に近い機体に大きなアームを取り付けた全くの未知の機体である。
- ゲリンは、迷わず新型機と交戦するために機体を振り向けると、一気にジムを加速させた。それに対抗するかのようにフクタ小隊のジムの各機も機体を翻す。
- ちらりと後方モニターを確認したゲリンは、思わず感嘆を漏らす。
- (やればできるんじゃない)
- コーンウェル准尉は、やや出遅れていたが、ナガレ准尉は、ゲリンの動きに追随してきていた。もちろん機体性能の差から、ゲリン少尉のジムに完全に追随できる機体はないのだが、援護を受けるには十分な機動をしてくれている。
- ボール隊を蹴散らした機体に向けてビームライフルを続けて発射する。しかし、想像以上のスピードに射撃解析値が追い付いておらず、ビームは、新型機の後方へ流れていく。新型機は、回避するどころかすさまじいスピードで一直線にジム隊の方へと突っ込んでくる。
- (豪胆なパイロット!!)
- ゲリンは、恐怖を覚えずにいられなかった。
-
- 「またぞろ、新兵器かいっ?」
- フクタ少尉は、ボールといえども瞬時に全滅へと追い込んだ機体が接近してくるのを見て、半ばあきれた。1機がゲリン小隊へ、もう1機が自分たちを指向されては艦隊直掩のための戦闘から自分自身を守る戦闘へと質が変わったのは仕方がないことだ。
- 速力も火力も、そしてパイロットの技量さえも上回っているであろう敵に、戦力を分散させるわけにはいかないからだ。
- ボール隊が殲滅されたことによって10機以上のガトル隊は、最終的な突撃を実施しようとしていたが、それを惜し留めることは、フクタ少尉にももはやできなかった。
- 「やる!?」
- 一瞬戸惑ったフクタ少尉とは、正反対にゲリン少尉のジムは、瞬時に突撃を開始していた。准尉の坊や達も、それに続いている。
- 「ちっ」
- フクタ少尉は、思わず舌打ちをしながらそれに遅れをとるまいとジムを加速させた。女だてらに恐怖の一つも感じないのか?とも思う。同じことはたった1機で3機のモビルスーツを相手取ろうとしているジオンのパイロットにも言いたかった。
- 先に射撃をはじめたのは、ジム隊だった。ほとんど乱射に近い射撃をあざ笑うかのように2機の新型機は、高速機動をし、野太いビームを2発3発と放ってきた。
- 大気圏内ならば、大地を揺るがすようなソニックブームが辺りを圧するに違いないビームだ。新型機が放ってきたビームのうちの一発が、フクタ少尉のジムの至近を通過する。胃が、ぎゅっと縮む瞬間だ。ビームを放ってきたと思った瞬間には、新型機は至近を通過していた。
- 反転機動をさせながら、フクタ少尉は、ゲリン小隊の占位する方向で熱核爆発が起こるのを見た。
- (おいおい、姉ちゃんがやられたんじゃあるまいな?)
- しかし、フクタ少尉がそれ以上他に気を配ることはできなかった。フクタ少尉が、想像するよりもずっと機敏な新型機の容赦ない攻撃機動に曝されたからだ。
|