- マーカム中尉は、ドップの翼を2度バンク(上下に細かく振る)させて、残存機の集合を促した。同時に周囲警戒を無意識のうちに行う。連邦軍機が、クモの子を散らしたように西の方へと避退していくのがキャノピー越しに見て取れた。
- 迎撃戦闘が終わった今、すぐにでも現状把握をしたかったが、2機のルッグンが振りまいたミノフスキー粒子のせいで、無線はほとんど使えない。
- 「ミノフスキー粒子も良し悪しだな」
- 集合しつつある友軍機を目で数えながらスコット・マーカム中尉は独りごちた。悪い点は、まさに無線が使えないことだ。指向性の強いレーザー通信は使えるには使えたが、役に立つとは言い難い。激しい空戦中の使用には全く役に立たない代物だし、通常の巡航時でさえ意志の十分な疎通は容易ではないのだ。そのせいで、戦闘が終わってもすぐに味方の損害が把握できない。そのことは、戦場にあっては不都合極まりがなかった。それでもどうにかなっているのは、これまでのところジオンが、航空戦をどうにか優勢に進めているからにほかならない。
- 良い点は、ドップのような不出来な戦闘機でも、格闘戦を行なえるようにしてくれる点だ。
- 「7機か・・・」
- 自分を入れても7機しか集合しなかったことに力なくつぶやきながら、マーカム中尉は、また別な考えも持つ。20機近くのフライマンタを9機のドップで迎撃して、3分の1は落としたのだからスコア的には上出来、いや申し分のないできだといえる。
- しかし、それでも2機墜とされたことの意味は大きいのだ。
-
- ミュンヘンのジオン軍基地に帰投したマーカム中尉は、その帰投途中に、結果が最悪なのを知った。
- 撃墜されたうちの1機が、開戦以来のベテランパイロットだったローレンス少尉だったからだ。もう1人は、先週補充されてきた新米のパイロットだった。どうせなら、2人とも新米パイロットであって欲しかったと、不謹慎なことを本気で考えるほど、ベテランパイロットを失った意味は、大きかった。
- 上空の雲間から奇襲を掛けたにもかかわらず2機ものドップを失ったのは、連邦軍機が、9機のドップに対して多すぎたせいだ。3倍もの連邦軍機は、今のジオン軍にとっては手に余るのだ。
- いや、数だけの問題ではない、とマーカスは首を振った。圧倒的な数の不利を少数の戦力で支えている現状で、ジオン空軍パイロットは、連実の出撃を余儀なくされていた。その結果、パイロットに疲労が蓄積していっているのだ。疲労は、時として判断ミスを誘い、それが戦場では死に直接結びつく。
- 開戦時であれば、3倍程度の連邦軍機はものともしなかったジオン軍のベテランパイロット達も、そのような理由で、この半年の戦いの中で櫛の歯が欠けていくように失われていった。
- その結果ドップの空力特性、言い換えれば操縦のしにくさ、を十分に把握したパイロットの減少という深刻な事態を招いている。代わって新しく補充されてくるパイロットは、ドップを飛ばすのがやっとという新兵でしかないからだ。
- 地球という実験場を持たないジオンが、主にコンピューターのシュミレーションだけで設計したこの格闘戦専用の戦闘機ドップは、その特異な形状からも分かるように非常に飛ばすのが難しい機体だった。それを補うために機体の各所に姿勢制御バーニアを装備して無理矢理正式化されたのがドップだった。ベテランパイロット達は、この姿勢制御バーニアを巧みに使うことによって従来の航空機ではありえない機動をし、連邦軍機を手玉に取り、これを撃墜してきたのだ。この姿勢制御バーニアを使いこなして自在に空戦を行えるようになるにはドップを自在に飛ばせるようになってなお何百時間もの訓練が必要だった。開戦時には、こうした訓練を見事に行いドップをまさに自由自在に機動させることのできるパイロットでジオン空軍は占められていた。
- 開戦当初のドップの圧倒的な強さの半分以上は、ドップを自在に操れるパイロットのおかげであり、ミノフスキー粒子のおかげだった。そのどちらが欠けても、ドップの活躍はなかった。現在、その絶対的要素のうちの1つが失われようとしているのだ。
- その2つの要素が完全に揃っていた開戦当初は、ドップは、圧倒的な強さを誇り、各地で制空権を絶対的に確保し、ドップのパイロット達をして地球の空を『ドップの空』と、表現なさしめた。
- しかし、現在では失われたベテランパイロットの替わりに補充されてくるのは、ドップをやっと飛ばせる程度のパイロットでしかなかった。飛ばすことができるということと空戦ができるということは、全くの別物であり前線が要望する要件を満たすパイロットは皆無と言えた。補充されてくるパイロットに、ベテランのようなバーニアを駆使した空戦技術は当然備わっておらず、逆にバーニアの使い方を誤って墜落するものまでいる始末だった。
- つまり、見た目には同じ機数のドップを揃えてはいても、実質的な戦力としては、漸減していくいっぽうだったのだ。
- それでも補充されてくるうちは良かった。戦線が、膠着し補給線が伸びていくと同時に、機体もパイロットも補充が滞り始めたのだ。
-
- 「中尉、レオーニ軍曹のドップはもう駄目ですね、遺棄するしかありません」
- 夜遅くまで機体の整備と修理を続けていた整備中隊のパントリアーノ少尉が、マーカム中尉の部屋にやって来たのは、日付が変わろうとするころだった。マーカム自身も戦闘報告を書き上げたところだった。
- 「駄目か?」
- 1機を諦めることは、この日の損失機が3機になることを表わしている。2週間前の補充以来、ドップの補充の目処がたっていない現在、1機のドップも無駄にはできないのだ。
- 「はい、エンジンの片一方に被弾していまして・・・連邦軍の30ミリ弾の不発弾です。運が良かったんですよ、軍曹は」
- それを聞かされて、マーカム中尉は、軍曹が助かっただけでも良しとするべきだと思い直した。軍曹は、3カ月前に補充されてきたパイロットであり、ようやくドップを自在に操れるようになってきた貴重なパイロットだからだ。
- そう、新兵でも補充されてくれば、鍛え上げることが可能なのだ。現状は、鍛え上げるべき新兵ですら補充されてこなくなりつつある。まさに、憂慮すべき事態だったが、前線の一指揮官では、どうにも出来ないことの一つだった。
- 「まあ、もう片一方のエンジンは、予備部品になりますし、全く無駄になるわけじゃないですよ。それに、今日は、2機飛べるようにしましたから」
- パントリアーノ少尉は、少しばかり得意げな顔になっていった。パントリアーノ少尉の整備中隊は、飛べなくなったり損傷したドップの機体の使える部分を組み合わせてどうにか飛べるドップをでっち上げるのも仕事にしているのだ。
- 「2機もか?」
- マーカム中尉は、顔を輝かせると心から礼を言った。「済まんな、少尉、ほんとに恩に着るよ」
- しかし、それでもドップの数は、全然たりなかった。その2機を戦力に加えてもミュンヘンのドップの総数でさえ47機でしかなかった。
- 実際に飛べる機体となると、そこからさらに割り引かなければならなかった。それでも、補給が滞りつつある現在、2機を再び戦列に加えて勘定できることの意味は大きかった。
- そのことを誰よりも良く知るマーカム中尉は、思わず右手を差し出すと堅い握手をパントリアーノ少尉に求めた。
-
- 「明日から、君がD中隊を指揮してくれ、イギリスから補充の機体とパイロットも来ているからな」
- ひどい戦闘、奇襲を受けて8機も墜されたのだ、から帰還してすぐに基地司令に呼ばれていると聞かされ、いきなり指揮官を任命されたのは、2時間ほど前だった。
- 女性であるゲリン少尉を指揮官に任命することに多少抵抗のそぶりを見せながらも、この司令は、そっけない言い方でその辞令を言い渡した。
- 中隊指揮官に任命されたことについては、なんの感慨もゲリン少尉は持たなかった。
- ゲリン少尉本人に言わせれば、開戦以来生き残ってきたことは確かだったし、今の部隊の状況、毎日のように戦死者を出している、を考えれば女性であるというだけで指揮官にしないということはナンセンスなのだ。
- 元のゲリン少尉の上官だった指揮官は、今日の戦闘で撃墜されてしまった。ミュンヘンのジオン軍基地を攻撃するために編成されたチューリヒの連邦軍空軍、第262戦闘爆撃機D中隊は、ミュンヘンにたどり着く前にドップ戦闘機の迎撃を受けたのだ。奇襲を受けたうえに、パニックに陥った262戦闘爆撃機D中隊は、相互支援を行うこともできずに、次々に被撃墜機を出すことになってしまった。指揮官機も、ゲリン少尉の目の前で、2枚の垂直尾翼に白い稲妻をあしらったドップの一撃を受けて空中で四散してしまった。
- 最初の一撃から幸運にも逃れたゲリン少尉達にできたことは、搭載していた6トンにも及ぶ対地上攻撃兵装を無為に投棄して、超低空を逃げ戻ることだけだった。
- そして、帰投できたフライマンタに、新たに補充されてきた機体をプラスして、見た目には、今朝、出撃前と同じだけの機数と頭数を揃えたのだ。
- (まあ、出撃までには、4、5日あるわ)
- 新しい部隊のパイロット名簿を受け取りながらゲリンは、独りごちた。今日、出撃を済ませたD中隊の次の出撃は、晴天が続いても4日先だ。天候が崩れれば、更に先になる。
- 案の定、翌日から天候は崩れ、ゲリンのD中隊が出撃するのは、1週間後になった。
-
- 空襲警報が鳴り始め、ミュンヘン基地が慌ただしく迎撃戦闘の準備を整え始めたのは、現地時間の午後4時少し前だった。
- 真っ先に、駆け出したのはこの日、スクランブルを担当することになっているパイロット達だった。それに遅れてマーカムの迎撃戦闘機中隊の全隊員が、滑走路を自分の機に向けて走っていく。
- 4日前に天候が回復して以来、3日連続の連邦軍の空襲に、半ばあきれながらもマーカム中尉自身も、滑走路脇の壕で発進準備を完了しているドップに全速力で駆け寄った。
- この日、連邦軍機を迎撃に上がることのできたドップは、12機、中隊全戦力である。パントリアーノ少尉の奮闘でどうにかマーカム中隊は、戦力を維持できているのだ。この時期の、他の部隊のドップの稼働率を考えるならば奇跡のような稼働率である。
- 連日の空襲に呆れながらも、事前に発見できたことについては、感謝しなければならない。昨日は、接近してくる連邦軍機を発見しそこない10機以上による連邦軍機の奇襲爆撃を受けてしまったのだ。おかげで、貴重なドップを7機も地上撃破されてしまい、基地の人員にも多数の死傷者を出してしまったのだ。
- レーダーが、本来の性能を発揮しないため、早期警戒は偵察機に頼るか、前線に配置した前線監視員に頼るしかなかく、警戒のルッグンが撃墜されてしまうか、監視員の目を擦り抜けられた場合、昨日のように奇襲を受けてしまうのだ。そういう意味では、まだルッグンが撃墜されるほうがいい。撃墜されることによって連邦軍の接近が予測できるからだ。
-
- 中隊全機、16機を率いてゲリン少尉は、中高度を進撃していた。天候の許すかぎり連日ジオン軍のミュンヘン基地を圧迫し続ける、これが現地の連邦軍の戦術だった。戦術というには余りにも拙劣だったけれど補給を十分に受けられないジオン軍にとっては有効だった。
- 中隊単位で、ローテーションを組んでの出撃は4日単位、晴天が続けばだが、で1回の出撃が各中隊にわまってくる計算だった。
- この3日間、A中隊から始まってC中隊までの出撃で、チューリヒの連邦軍は、合計で11機のフライマンタを失っていた。昨日の成功した奇襲攻撃では、全く損失が出なかったことを考えれば、まだまだジオンの迎撃能力は、侮れないものがあるということだ。それでも、開戦時の空戦に比べれば連邦軍パイロットの生還率は、随分上がっているのだ。
- そして戦果の方は、地上撃破も含めるならば実に18機のドップと3機のルッグンを撃墜しているのだ。もっとも、ドップの18機というのは多少割り引いて受け取らなければならない。空戦での撃墜報告は、どうしても多め多めになるからだ。
- 「各機、上空警戒を怠るな!」
- ゲリン少尉は、上空を覆い始めた雲を気にしながらいった。
- いやな雲、そう思った瞬間、雲間からジオン軍の迎撃機、ドップが降ってきた。
-
- 緊急発進をしたマーカムは、アフターバーナーを大胆に使って指揮下のドップとともに高度を5000フィートまで一気に上げた。雲を突き抜ければ、そこは下界の天候とは関係なく、いつも晴れている。そして、眼下には所々穴を開けた雲海が壮大に広がっている。
- 雲海は、マーカムの好きなものの一つだった。コロニーの中では絶対に見ることのできない風景の一つだからだ。地球に降下して以来、数々の感動的なシーン、たとえば夕焼けもそうだ、を色々見てきたが、雲海ほどマーカムを感動させたものはなかった。
- 雲海は、壮大であるとともに、味方機の接近を敵から隠してくれる絶好の隠れみのにもなる。しかし、逆に敵をも隠してしまうのだけれど。
- 前線監視員から送られてきた報告が正確ならば、そろそろと思ったちょうどその時、マーカムは雲間から連邦軍の標準的な戦闘爆撃機フライマンタの編隊を発見した。
- 4機編成のダイヤモンド編隊が4つ、つまり16機のフライマンタが、眼下を亜音速で飛行しているのが見て取れた。
- 機体を3度軽くバンクさせ、敵の発見を指揮下の全機に伝えると、マーカムは、翼を翻し、急降下に移った。一瞬、視線を後方にやり、全機が続いてくるを確認すると、マーカムは、眼下の連邦軍機に全神経を集中させた。
- 狙うのは、先頭を進んでいる指揮官機、指揮官機さえ撃墜してしまえば、敵はパニックに陥るに違いないからだ。
- 「ちっ」
- 思わずマーカムは舌打ちをした。降下を始めるやいなや連邦軍機は編隊を解いたからだ。
- つまり、連邦軍の目敏い誰かがこちらを見つけたということだ。しかし、上空を占位しているのは、マーカムたちだった。絶対的優位が崩れたというだけで、いまだに優位にあるのはマーカムたちなのだ。
-
- 「ブレイク!!」
- ゲリンは、敵を発見すると同時に編隊を解くことを命じた。同時に、自分も右方向へ急降下をした。ちらりと後方を振り返り、2番機のランドルフ軍曹機が、自分に追随しているかどうかを確認する。いまのところは、問題がないようだった。
- しかし、それは長くは続かなかった。
- 「少尉、真上から来ます!!」
- 軍曹のしてくれた最後の警告を聞くと同時に、返事をするよりも早くゲリンは、機体を急激に左へ旋回させた。急激な旋回でフライマンタのスピードが落ちる。同時に、火線がすぐ脇を駆け抜け、続いてドップが自らの発射した機関砲弾を追うように下方へと飛び抜けていった。
- ゲリンは、最初の一撃を間一髪躱すことが出来たが、誰もがそうではなかったようだ。視界の隅におそらくはランドルフ軍曹のものと思えるフライマンタが派手に爆発するのが見えた。
- (ちっ)
- 早くも1人の部下を失った・・・基地司令の嫌みを覚悟し、ゲリンは、機体に速度を再び与えるべくスロットルを目一杯押し倒した。
- 下方へ飛び抜けたドップ、通常の機体ならば、高度を急速に落とし、再び攻撃を受けるまでには時間的な余裕があるのだけれど、ドップだけは違った。それを証明するように、後方を振り返ったゲリンの目に、信じられない機動をして後方を占位しようとするドップが見えた。
-
- マーカムの後ろには、グラーフ准尉のドップが続いていた。マーカムと同じ歴戦のパイロットだ。
- マーカムの狙った指揮官機は、急激な、マーカムが思った以上の、旋回でマーカムの一撃を寸でのところで躱した。躱された瞬間には、マーカムは、バーニアを駆使して、ドップの高度が必要以上に下がるのを押し留める。本来なら500フィートは下がってしまう高度の低下を、それで200フィート以下に押し留めてしまう。
- グラーフ准尉の狙ったフライマンタが、炎をまき散らしながら四散するのを認めつつマーカムは、自分も機体の撃墜マークを増やすために機体を強引な旋回、これもバーニアを使った無理矢理な旋回である、で連邦軍の指揮官機の方に振り向けた。
- 指揮官機は、更に高度を落としスピードも失っている。高度を下げつつスピードの回復に努めようとしている様子だったが、簡単にはいくはずはなかった。
- 機体の方位を修正すると、アフターバーナーに点火し、一気にその間合いを詰めた。
-
- 事前に気が付いたとはいえ、奇襲を受けたことには変わりなかった。ドップは、既に後方を占位しつつある、ゲリンは、その時になって自分が、まだ投棄すべき爆弾を抱えていることに気が付いた。このままでは撃墜されてしまう。
- しかし、同時にただ捨てるだけではもったいない、ひらめきがゲリンの脳裏をよぎった。
-
- レチクルに必死に逃れようとするフライマンタが納まりつつある。納まった瞬間が、連邦軍指揮官機の最後になる。右旋回する、そう思った瞬間、マーカムの視線は、フライマンタから飛び出したものに一瞬注意を奪われた。右へ旋回すると見せかけて、機体を瞬時に横倒しにし、そのまま左へと旋回降下をしたフライマンタの爆弾槽が開き、爆弾がばらまかれたのだ。
- 爆弾槽を開いたことで急激に失速したフライマンタをマーカムは、追い越してしまった。一瞬とはいえ、そのフライマンタを視界から逃してしまったことに怒りを感じつつ、マーカムは、機体に再び強引なバーニア機動をさせ、再度フライマンタを視界へと捕らえた。
- (もう逃がさない、必ず撃墜してやる)
- マーカムは、心で叫んだ。
-
- 右に旋回、同時にフラップを急激に操作して機体を横倒しにすると同時に爆弾槽を開き、爆弾を投棄させる。激しいGの中でこれだけのことを奇跡的にもこなしたゲリンは、そのまま機体を強引な左旋回へともっていった。やわな作りの機体であれば空中分解しかねない機動である。フライマンタの頑丈な機体なればこそである。
- 機体を右へと急旋回させ、身軽になったフライマンタを上昇させようとした瞬間、正面を左から右へと横切ろうとしたドップが、ゲリンの視界に入ってきた。
- 「墜ちちゃえっ!!」
- 叫んだのが先か、発射ボタンを押したのが先か?見えた瞬間には、ゲリンは、行動を起こしていた。
- そのドップは、まともにフライマンタの30ミリ機関砲の射線に自分から突っ込んでいった。ドップの大きな特徴的な風防が一瞬で粉々に砕け、更に機体の後部が30ミリ機関砲弾によって粉砕される。
- 「1機、撃墜!!」
- ゲリンは、小声で喝采を上げた。しかし、喜んでばかり入られなかった。自分をしつこく追撃してきているドップが再び、後方を占位しようとしていたからだ。
-
- マーカムは、自分を呪った。
- 自身が撃墜しそこねたばっかりに味方が1機、撃墜されたからだ。ドップが派手に炎を撒き散らしながらヨーロッパの大地にと消えていくのを横目で見やりながら、マーカムは、3度目の攻撃機動に入った。
- (今度こそは逃さない)
- マーカムは、レチクルいっぱいになったフライマンタを睨み付け、心の中でつぶやいた。
-
- よほどのベテランに狙われてしまったらしかった。どういう機動をしても、振り切ることは不可能だった。
- 「ここまで?」
- ゲリンの頭の中を走馬灯のように過去の出来事が駆け巡っていく。それでも身体は、敵の攻撃から逃れようと、ありとあらゆる機動をフライマンタに要求し続けた。そして、右旋回から急上昇に移ろうとした瞬間、機体は激しい衝撃に襲われた。
-
- 確実に撃墜してやる!!
- そう心に誓ったマーカムは、目の前のフライマンタが、右旋回から急上昇に移ろうとした瞬間に機関砲の発射ボタンを力いっぱいに押し込んだ。
- 曳光弾が、何発か空間に吸い込まれた後、面白いように次から次へとドップから放たれた機関砲弾は、フライマンタの機体へと吸い込まれていった。フライマンタの機体から、破片がばらばらと飛び散っていく、煙を吐き、火を吹くまでにはいくらも掛からなかった。
- 推力を失ったフライマンタは、命を失った鳥のように地上へと落下し始めた。
- それを見届けると、マーカムは、新しい生贄を求めて機体を旋回させた。
- しかし、その時には連邦軍機は、元来たほうへと逃げ散っていくところだった。追撃して行ってもっと多くの連邦軍機を地上へと叩き付けねば気が済まなかったが、そうするためには、余りにもドップの航続距離は短かった。
-
- 十数発もの機関砲弾を受けては、さすがのフライマンタも撃墜は免れなかった。ありとあらゆる計器が異常を指し示し、エンジンは、完全に止まってしまった。ゲリンは、なんとか機体をコントロールしようと努力したけれど、エンジンが1グラムの推力も出せないのではいかんともしがたかった。
- シートの肩口にある脱出用のグリップに手をやると、躊躇なくゲリンは、それを力いっぱい引っ張った。どうしようか?などと考える余裕がないくらいにフライマンタの高度が下がっていたからだ。
- ドンッ、鈍い爆発音とともにキャノピーが、吹き飛び、わずかに遅れて火薬式の脱出シートでゲリンは、シートごと空に放り出された。
- シートが、身体からはずれ、続いてパラシュートが開く、開いたと思った瞬間には、ゲリンは、森の梢の中に吸い込まれていた。
- ベキバキベキッ
- 枝がクッションになっていなければ、骨の2、3本が折れるところだったかも知れなかったが、現実にはゲリンは、多少かすり傷を負ったが、無傷だった。
- パラシュートのハーネスを外しながら、自分が原隊に復帰すのにいったいどれほど掛かるだろうか?と、考えゲリンは、途方に暮れた。1週間は掛かるだろう。悪くすれば1カ月かかるかもしれない。
- 帰隊するころには、ひょっとすると、戦死扱いになっているかも知れないが、とにかく原隊に復帰することが先決だった。原隊復帰したら今度は、こんなへまをしないとゲリンは、心に誓った。
- しかし、無事に原隊にたどり着いたゲリンが、再びフライマンタに搭乗することはなかった。それが、わかるのはまだ2週間ほど先のことだった。
-
- 3機が、編隊に戻ってこなかった。
- 勝てない・・・。
- マーカムは、帰投するために組んだ編隊に、復帰できなかった機体を数えてそう思わずにはいられなかった。ミュンヘンへと向かいながらまたしても機数を減らしてしまった自分の編隊が、今日も勝利したにもかかわらず少しづつ、しかし、確実に戦力を殺がれていくのを感じ、撃墜数では勝ったにも関わらずその思いは、拭えなかった。
- 明日は?休めるだろうか?
- 答えは、ノーだ。
- 今日も、少なくとも7機は叩き落としたにもかかわらず、連邦軍機は何事もなかったかのように、明日も今日と同じ数だけ揃えてやってくるはずだった。
- それなのに、自分たちは、減ってしまった3機を補充できるかどうかさえ怪しいのだ。
- 自分たちが、決して先の見えることのない戦いに身を投じているのに気が付きながらもマーカムにはどうすることもできなかった。ただ、マーカムにできるのは、マーカムが飛び続けられるかぎり、空に上がり、連邦軍機を1機でも多く空から叩き落とすことでしかないのだ。
- 『ドップの空』が、いつまで続くのか?マーカムにはそれがそれほど長く続くとは思えなかった。いや、もう『ドップの空』では、ないのかも知れない。そういう思いを頭から振り払いマーカムは、帰投するために翼を翻した。
-
-
0079u.c.まだ、戦線が均衡していたころの話しである
|
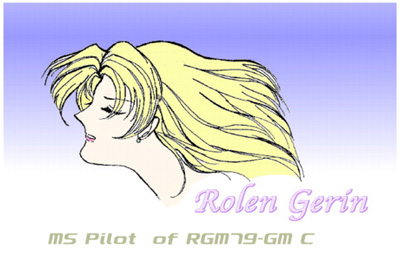
![]()
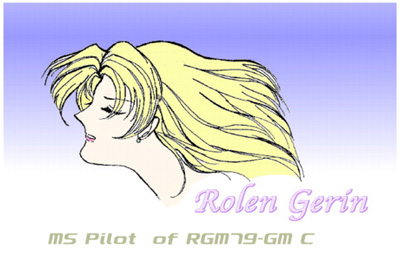
![]()