- U.C.0079.11.10
-
- 「た、大佐っ・・・」
- ア・バオア・クーの一角を占めるWフィールドの防衛の一端を担う、第484大隊、通称空間雷撃艇大隊の司令室に、副官のトゥーフォン中佐が、駆け込んできたのは、地球でオデッサが陥落した翌日だった。
- 「何か?」
- 大佐と呼ばれたかっぷくのいい将校は、顔も上げずに、書類にサインを続けながらいった。ブラウンの髪に白いものが混じり始めてはいるが、元々持っている威厳を損なうものではなくかえって風格を添えている。ギレンにも、キシリアにも組しない生粋の軍人だった。
- 顔を上げなかったのは、元来、何かにつけて大げさに言うきらいのある中佐のことに慣れているせいであった。
- 「マ・クベ大佐が、地球を脱出したそうです」
 さすがに、レモー大佐は、手を止めて、顔を上げた。 さすがに、レモー大佐は、手を止めて、顔を上げた。- 「地球を?」
- 「ハイ、オデッサが落ちたようです」
- それを聞くとレモー大佐は、黙ったまま背もたれにゆっくりと背を預けると目を閉じた。
- 「分かった、下がっていい」
- そういっったのはしばらく経ってからだった。中佐を下がらせると、レモー大佐は、イスを回転させ、壁の方に向き直った。壁には、地球を中心にした宙域図が掲げられていた。
- オデッサ、ヨーロッパロシアの一大資源地帯であり、そこにはジオン軍地球方面軍第10軍団が制圧していた一大鉱山基地があった。オデッサは、キシリア少将直属のマ・クベ大佐の管轄下にあった地球上で最も重要な拠点の1つだった。
- 当初かくかくたる戦果を挙げ続け、占領地を拡げ続けた地球侵攻軍だったが、連邦軍が、その体勢を整えるとともに進撃スピードは落ちていった。それは、キシリアに寵愛され、優先的に装備を割り当てられていたマ・クベ大佐麾下の第10軍団にあっても例外ではなかった。開戦して、半年を過ぎるころには地球上の全ての戦線は膠着してしまった。
- そして、いったん膠着した戦線は、2度と以前のようにドラスティックに動こうとしなかった。その膠着した戦線を維持するために消耗していくジオン軍の一方で、連邦軍は反攻のための戦力を着々と蓄えていることは余りにも明白だった。その兆候は、8月以降からルナ2宙域や、ヨーロッパ戦線の一部で見られていた。連邦軍の、明らかに量産型と思われるモビルスーツが、部隊単位で姿を見せ始めていた。しかし、軍の公式発表では、それは試作型であり、大量に戦線に現れてくるのは、早くても来年の夏以降だということになっている。
- 問題は、反攻を押さえられるかどうかということではなく、それがいつ、どこで始まるかということだった。少なくともまともなジオン軍の高級将校であれば、誰でも理解していることだった。いかに、ギレン閣下が、高尚な演説を垂れようとも、それは、リップサービスでしかなく、今後投入されるはずの新型兵器にしてもそれが戦線全体に対していったいどの程度の影響力を及ぼすのかは、全くの未知数でしかなかった。どんなにリップサービスがなされようとも、いまだにジオン軍の主力は、ザクであるのだ。
- そして、恐れていた連邦軍の反抗は、ジオンの首脳部が考えていたよりもずっと早い先週の金曜日に始まったのだ。それは、最も効果的かつ、戦力規模の大きいヨーロッパロシアに向けて、始められた。
- それ日から専ら、ジオン軍の高級将校達にとって非公式な席での話題はオッデサのジオン軍が勝利するか、ということではなく、いったいいつまで持ちこたえられるかということだった。公式発表で、当初予想した以上の戦果を第10軍団があげていると聞かされても、彼らの中では、連邦軍を退けるなどという希望的観測を持つものは皆無だった。第10軍団の崩壊が先に延びたに過ぎないことをよく知っていた。
- しかし、どんなに最悪の結果になろうとも、まさか、オデッサが、ほんの3日で崩壊してしまうとは予想だにしないことだった。最も悲観的な予測でも10日は、持ちこたえるだろうというのが大方の予想だったからだ。
- そして、オデッサが落ちてしまった今、次の戦場は、宇宙になる、というのは明白だった。地球上では、オデッサ以上に戦略的に重要な地域などはありはしないからだ。再び、宇宙が戦場となったとき、自分の部隊がどうなるのか?それは、決して想像してみて楽しいものではなかった。
-
- 同じ頃、ア・バオア・クー内にある484中隊の宿舎の一室で、アルフォンス・ハリソン中尉は、ゆっくりと目覚めた。こんなふうに、ゆっくり目覚められるのは、今日が非番であるからにすぎない。普段であれば、とっくに軍務、とは言っても、現在の484大隊にはやるべき任務がないのだけれど、に就いている時間だった。
- 隣には長い睫毛が魅力的なリンダが、うつ伏せになって無邪気な顔をこちらに向けてまだ眠っていた。リンダは、同じ隊の女性補給士官であり、本来ならば、こういった形での同室は、認められてはいないのだが、慣例として許されているのだ。
- シーツの下のリンダは、昨日、そのまま寝てしまったので何も身に付けてはいなかった。ハリソンは、ゆっくりと手を伸ばすと、リンダの張りのある肌に手を這わしていった。そして、最もくびれた部分に届くと、そのくびれを楽しむように今度は、指を優しく動かした。
- 起こさないようにしたつもりだったが、くすぐったかったのか、リンダは、軽く伸びをして、閉じていた目を開け、ハリソンを見つめると、悪戯っぽく笑った。その微笑みは、十分すぎるぐらい色っぽい。ブルーの濃い瞳は、まだ物憂げだったけれど、それすらもリンダの魅力を引き立てていた。
- 「おはようございます、中尉」
- その少し低めの声がハリソンの好みだった。やや擦れているのは、起き抜けだからだ。ウエーブしたセミロングの艶のある赤毛もハリソンが気に入っている点だった。
- 「おはよう、少尉。お目覚めはいかがかな?」
- 「中尉に起こされたんですもの、もちろんいい目覚めに決まってるじゃない」
- そう言って、リンダは、屈託のない笑いをみせて、両ひじをついて身体を少し浮かせた。そうすると、リンダの形のいい胸がハリソンの目に飛び込んできた。
- 「ねえ、中尉・・・」
- リンダが、甘えた声で何かを続けていおうとしたとき、呼集のアラートが、鳴り響いた。
- 「・・・というわけだ」
- ハリソンは、少しばかり恨めしそうに、アラートを鳴り響かせているスピーカを見上げた。
- 「残念だわ・・・」
- それだけいうと、リンダは、ベッドから飛び出しシャワールームに消えた。
- 消えるまでのほんのひととき見えた脚も素直に綺麗に伸びていて、ハリソン好みだった。要するに、ハリソンは、リンダの全てが気に入っていた。
-
- 1時間後、ブリーフィングルームには、第484大隊の主だった面々が集まっていた。もちろん、ハリソン中尉も、その中の1人だ。第2中隊の第2小隊長だからだ。他には、ジッコの各小隊長、ザクのパイロット全員が、集められていた。
- 正式には、単に第484大隊だが、部隊に所属する兵士達のほとんどは、部隊を通称名、484空間雷撃艇大隊と呼んでいた。大隊の主戦力であるガトル戦闘爆撃機を、昔の雷撃艇になぞらえているからだ。確かに、ガトルの主武装である片舷2基づつ、計4基のミサイルを発射するさまは、爆撃というよりは、魚雷を発射するのに似ていなくもなかった。
- 元々の484大隊は、特設空母オリノコの搭載部隊だった。1週間戦争、ルウム戦役にも母艦とともに参加した歴戦の部隊である。しかし、敵艦に肉薄してミサイル攻撃を行うガトルの損耗率は、常に大きかった。オリノコの搭載部隊とてその例外ではなく、1週間戦争では、半数にも及ぶガトルを失った。さらに補充を受けた後に参加したルウム戦では、母艦であるオリノコをも失い、同時に、定数27機のうち、18機のガトルをベテランパイロットとともに失った。以降は、母艦を失ったオリノコ所属のガトル隊は、1防衛部隊にと格下げされア・バオア・クーのWフィールドに配備されることとなった。
- そして、484大隊として、正式にア・バオア・クーの防衛についたのは、もう半年以上も前になるのだけれど、今日までガトルの定数の27機を満たしたことはなかった。同じように、ガトルを支援するために配備されているジッコも9機の定数を満たしたことはない。本部小隊と、偵察小隊が持つザクも、6機のうち、4機が05タイプであり、これだけを見ても484大隊にア・バオア・クーが何を期待しているのかは十分に分かった。
- ハリソンは、そういった中で開戦より生き残っている数少ないガトル乗りだった。大隊の中ではハリソンの他には、もう7人しか生き残ってはいない、貴重なベテランガトル乗りだった。
- 補充されてきたガトルパイロットは、そんな彼らから見れば、ひよっこもいいところだった。そんなひよっこの機長も、何人も混ざっている。ルウム以降、484大隊は、実戦を経験していないわけだから、必然的に彼らは全員が、素人の集団でもあった。
- 大隊所属のザクのパイロットも、本部小隊の指揮官を除けば全員が、若い。若いことの全てが、悪しきことではなかったが、ハリソンに言わせれば、戦場にでるべき年齢ではないはずだ、ということなのだ。
- 無論、彼らも訓練は受けてはいるが、ハリソン達から言わせれば、そんなのは、お遊びにしか過ぎないとしか思えなかった。
-
- 全員が、集まり、着席するとレモー大佐は、地球で起こったことと起こりつつあることについて話始めた。
- 話が進むにつれ、古参の勇猛をもって知られるガトル戦闘爆撃機のパイロット達ですら、その表情はさすがに険しいものにならざるをえなかった。
-
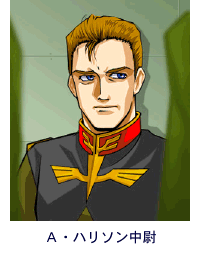 そして、同じ内容を各隊の指揮官は、直属の部下達にしなければならなかった。 そして、同じ内容を各隊の指揮官は、直属の部下達にしなければならなかった。- 「そんな・・・」
- 小隊の中でも楽天家を自任するケイオス軍曹が、細い目を思いっきり開いて首を振りながらいった。軍曹は、3番機のサブパイロットだ。今の今まで、軍の公式発表を信じていたのだから無理もない。
- ケイオス軍曹だけではなく、この日食堂に集まった484空間雷撃艇大隊第2小隊の面々は、ハリソン中尉の話を信じられない思いで聞いた。恐らく今ごろ大隊の他の兵士達も同じ思いをしているはずだった。
- 「信じろっていわれても、昨日までの軍の発表じゃあ・・・」
- そういって絶句したのは、ハリソン中尉機のサブパイロットを務めるブレン曹長だ。
- ハリソン中尉と同じ古参のパイロットのリッツェン少尉だけは、特に表情を変えずに黙ったままだった。
- 「軍の発表の全てが正しいわけではないということだ」
- ハリソン中尉は、他の5人の顔を見回しながらいった。
- 「次の目標は、カリフォルニアですか?」
- リー曹長は、連邦の次の動きを聞いた。曹長は、リッツェン少尉のサブだ。
- 「甘いんだよ」
- 曹長の問い掛けに対して、リッツェン少尉が短くいった。
- 「何が、甘いんですか?」
- 言われてリー曹長は、ちょっとばかりむっとした表情で後ろに座っていたリッツェン少尉を振り返った。イスに浅く腰を掛けたリッツェン少尉は、足を組んで、不敵に笑っていた。
- 「甘いから、甘いと言った。連邦が、そんな回りくどいことをすると思うのか?」
- 「少尉、よすんだ。曹長も、むきにならなくってもいいだろう」
- いつものように、若い兵を子供扱いする少尉を、止め、またその挑発に乗ろうとする曹長を、ハリソン中尉は、苦笑いしながら止めた。特にこの2人はそうなのだ。
- 「だが、少尉のいうことが正しい。次の連邦軍の主攻は、地球上のどこかではなく、この宇宙になる」
- 「地球を、制圧しないままにですか?」
- 驚きを隠せない表情で、そういったのは3番機のメインパイロットのアルダマ准尉だった。准尉は、他の多くのガトルパイロットと同じように学生上りで純粋にジオンを信じている。オデッサを失ったとはいえ、いまだ地球上の多くを抑えているのは、ジオン軍のはずだと信じているのだ。ア・バオア・クーの、多くの兵士がそうであるように、准尉も、地球のことについては、軍の公式発表以上のことは知らない。
- 北米を制圧している第11軍団が、木馬の追撃戦の中で大損害を受け、その後の補給が、不十分であること。アフリカ戦線を担当する第9軍団には、通常の補給自体が滞っていること。地球のあちらこちらで、伸び切った戦線が、繕う間も無く崩壊を始めていること。連邦軍も、量産型のモビルスーツを大量に前線に投入始めたこと。そのモビルスーツが、ほとんどのジオン軍モビルスーツよりも高性能であること。
- こういったことの全てを知らなかった。彼らの知っていることといえば、軍の発表する景気のいい戦況でしかないのだ。
- 「連邦にとってはな、ついでのことなんだよ。余った戦力で地球をやれるのさ」
- リッツェン少尉が、殊更なんでもないように言った。それに対して、リー曹長が、何かをいいたそうにしたが、ハリソンは、それを視線で制した。
- 「しかし」ハリソンは、少し大きな声でみんなの注目を集めてからいった。「宇宙で補給に苦労するのは、連邦軍の方だ。だろう?狭い地上なんて、連邦のクソ野郎にくれちまえばいいのさ」
- そういって、みんなを見回したハリソンは、続けて今後の部隊の訓練計画について話始めた。今は、戦況について議論しているときではなかったからだ。
- しかし、そのハリソン中尉にしても、連邦軍の物量が、どんなに圧倒的なのかを完全に理解しているわけではなかった。
|