- (ソロモン戦)12月17日
-
- (さすがに、新型補給艦を投入するだけのことはある)
- ナガレ准尉は、つい1時間前までは何もなかった空間に出現しつつある一大ページェントを眺めながら思った。確かに、凄いことなのだ。万の単位で整然と並べられていく、鏡は。
- しかし、それで本当にソロモンに打撃を与えられるのかどうかとなると、ナガレ准尉にはよく分からなかった。確かに、理論的には分からないでもない。ようは、虫眼鏡で太陽光を集めて熱するのと何ら理論的には変わらないのだ。分かってはいても岩石でできた宇宙要塞に対して果たしてどの程度の威力を発揮するのかを想像することは難しかった。
- ただ、この大量の鏡を護るために4個戦隊もの戦力を、その搭載モビルスーツとともに充てている以上、それなりのことはあるのだろう。だからといって、パイロットたち全員が、この任務に満足しているはずがなかった。
- 「納得、いきません」
- 小隊指揮官のゲリン少尉は、54戦隊司令からこの任務を聞かされるなり言ったものだ。それは、多くのパイロットの意見を代弁してもいた。特にジムのパイロット達は、そうだった。中には、コーンウェル准尉のように、後方勤務になったことに安堵するものもいるにはいたが、多くは、血気盛んな若者であり、前線に出てジオン軍を打ち負かすことを望んでいたのだ。もちろん、そこには、戦死の危険が常につきまとうことをどれだけ認識している者がいたかどうか、それはまた別の問題だ。
- ナガレ准尉は、どちらでもなかった。確かにゲリン少尉の言うことももっともだったけれど、彼自身は、与えられた任務を、それがたとえどのようなものでも全力でやればいいと思っていたからだ。ただそれが、鏡の防衛になるとは思って見ていなかったのだけれど。
-
- 幸か不幸か、54戦隊を含むソーラー・システムの直衛隊は、直接戦火を交えることなく、ソロモン戦を観戦する立場で、終えた。
- 時折、衛星ミサイルが至近に迫ったことはあったもののそれらは、直接脅威を及ぼすものではなかった。
- 後の公式発表では、連邦軍は、戦闘の最終段階で旗艦を撃沈されるというアクシデントがあったものの当初予想されていた損耗率をはるかに下回る値でソロモンを攻略できたと発表した。
- しかし、後に発表された内容がどの程度真実を反映しているのかは、当時最前線にいた彼らに分かるはずもなかった。
- ただ確かなことは、ミラーを警護していた部隊以外には、無傷な部隊は、ほとんどなかったということだけだった。ミラーを警護していた54戦隊を含む4個戦隊は、少なくとも掛値なしの無傷な完全編成の部隊であることは間違いなかった。
- このことは、これらの戦隊が直接、星1号作戦時の進攻ルート上の哨戒及びジオン軍部隊掃討任務に投入されることに繋がった。何故なら、搭載モビルスーツの一部を失ったり、母艦自体を喪失した部隊を再補充して投入するよりもよほど迅速にその任務に当てることが可能だったからだ。
- そして実際に、54戦隊は、1隻の旧式な補給艦と艦外係止の新編成のモビルスーツ隊を付与されてサイド5空域の哨戒および残敵掃討任務に当てられることになった。
-
12月18日 ア・バオア・クー
-
- 誰もが想像もしなかったスピード、わずか1時間、でソロモンが落ちてしまったことは、ジオン全体に波紋を投げ掛けた。とりわけその影響を大きく受けたのは、今後前線となるア・バオア・クーでありグラナダの若い兵士達だった。
- その影響は、484大隊においても例外ではなく、昨日以来大隊の兵士達のほとんどを無口にさせていた。
- 「参りましたね」
- ブラドー中尉は、そういった状況に肩をすくめた。今度ばかりは、若い兵士達を気分転換させるには、骨が折れるだろう。彼らの心の防波堤でもあったソロモンは、もろくも崩れ去ったのだから。
- 今夜、レストルームに来ている将兵の数は、心なしか少ない。いつもならば、多少羽目を外した若い兵士の嬌声が聞こえたりするものだが、さすがに今夜ばかりは静まり返っている。
- 「全くな」ハリソンも、全くもって覇気のなくなってしまった若い兵士達を、見やって言った。「ドズル中将も、罪なことをやってくれるぜ」
- 特に申しあわせたわけでもなかったのだけれど、たまたま2人の中尉は、同じ時間にレストルームにやって来たのだ。
- 昨日以来、いや正確には、ソロモンが陥落した直後からドズル中将が、満足な救援を送ってこなかった本国に対する当て付けにソロモンを半ば放棄する形で連邦軍の攻勢の前に明け渡してしまったということがまことしやかに噂されていた。
- ハリソンには、そのことが分かっていた。それは半分本当で半分は嘘なのであろうということも。
- 徹底抗戦をすれば、それなりに連邦軍を拘束することができたのだろうが、その代償としてソロモンの将兵の大半は、ソロモンと運命をともにすることになったはずだ。
- だが、実際には少なくない将兵が、ソロモン空域から生還しているのだ。つまり、戦っては見せたが、本国の補給が十分でなかったためにいとも簡単にソロモンは落ちたのだよ、ということをドズル中将は、自らの命をも供する形で本国、ひいてはギレンに示して見せたのだ。
- つまりは、ドズル中将は、自分のメンツを立てるためにソロモンを使ったということだ。そのおかげで、ア・バオア・クーにおける兵士の士気は、最低になってしまったのだ。
- 「どうしたもんでしょう?」
- 同じ中尉ではあっても、ハリソンの方が先任であるためブラドー中尉はやや丁寧な言葉使いをしている。
- 「同じ手を使えないってことだけは確かさ」
- 以前は、まだまだここが戦場となるまでには時間があり、それまでには、十分な訓練を積み、自信をもって戦闘に加入できるようにしてやると見栄を切れたのだ。しかし、今はもう、そんな時間も余裕もないのは素人同然の彼らにもわかる。
- 「いつ始まると思う?」
- ハリソンは、自分でもあらかじめ答えを出してある質問をした。
- 「連邦軍の攻勢ですか?」
- 「そうだ」
- 「長くて1カ月、ソロモンとア・バオア・クーの軌道の関係を見れば多少早すぎる嫌いはありますが、6日後ですね」
- それは、ハリソンの考えと全く変わるところはなかった。つまり今から6日後というのは、ソロモンとア・バオア・クーの軌道公転の関係上、もっとも接近するのだ。その後は、ソロモンとア・バオア・クーは、お互いに離れていきソロモンから出撃するであろう連邦軍は、ア・バオア・クーを追い掛けることになる。
- 推進剤をより多く消費することになり、効率的とは言いがたい。いかに連邦軍の物量が豊富だとはいっても必要になってくる推進剤の量は、軌道遷移のことも考慮するならば段違いになる。
- 1カ月というのは、戦力の再編成を考えればそのぐらいジオンならばかかることを考慮してのことだ。しかし、ジオンに比べれば数十倍の国力を誇る連邦軍が、果たして1カ月待つかどうか甚だ疑問だった。
- 「6日後・・・だろうな」
- ハリソンは、都合よく考えないことにした。連邦軍が、こちらの都合に合わせてくれることを望むのは、いかにもナンセンスだからだ。
- 「しかし、戦力不足は否めません。ここを攻めるにはいかにも・・・という気はします」
- ソロモンで失われた連邦軍戦力は、決して少ないものではないはずだ。補給拠点という意味合いの大きいソロモンとは違い、このア・バオア・クーは、正真正銘の宇宙要塞である。ソロモンを落とした残余の戦力では、手に余るのは間違いがなかった。
- 「そうだな、このままだったら6日後というのはいかにも無理だろうな。できんだろう、常識的に考えればな」
- ハリソンは、知らなかったが、連邦軍の反攻戦力の胎動は、既にジャブローで始まりつつあった。地球から宇宙への最大の質量移動を始めようとしていたのだ。24時間、たったそれだけの時間で、連邦軍は、ア・バオア・クーを圧倒することが十分に可能な戦力を宇宙へと展開しようとしていたのだ。そして、それができるだけの物量と能力を連邦軍は、持っていた。
- 「できないことを祈りますよ、全く」
- 最後に、ブラドー中尉は、そういうと席を立った。
- ハリソンも、それにつられるように席を立つと、2人揃って士官室のあるブロックへと歩き始めた。肩を並べて部屋に戻る間、2人は一言も口をきかなかった。なぜなら、無理だろうと思う反面、心のどこかでそれを連邦軍が実現してしまうのではないか?という気持ちを2人とも捨てきれなかったからだ。
-
- 部屋に戻ったハリソンは、明かりもつけずにベッドに座り込むとア・バオア・クーについて考えを巡らせ始めた。リンダによると、古参のモビルスーツ部隊、ほとんどはギレン直属、の引き抜きは、先週いっぱいで終わったらしい。しかし、新しいモビルスーツ隊も、時を同じくしてやってこなくなったらしい。
- 「子供の顔を見なくなって、ほっとしたわ」
- リンダは、そう表現した。
- 補給部隊の話を総合すれば、ア・バオア・クーのモビルスーツ戦力は、数字上はアップしたことになる。しかし、その内容はお寒いかぎりだった。ベテランパイロットが多数抜けた後にやって来た代替部隊のほとんどは、学徒動員のパイロットか、錬成途中の教導大隊から抽出された兵士だったのだ。それを考えれば、総合戦力は、むしろダウンと考えるべきだった。
- では、本国は、ア・バオア・クーをも捨て石にするのか?
- しかし、それは、昨日知らされた新しい情報のことを考慮するならばありそうにない。ドロス級空母の1隻を定数を満たしてア・バオア・クーに派遣するというのだ。ドロス級は、空母と表現するよりは、もはや移動要塞といったほうが早い。動けるというだけであって、艦隊運用などは始めから考慮されずに建造された空母である。ガトルを100機近く、主兵装のモビルスーツを200機近く運用できる能力は、まさに移動要塞と呼ぶのに相応しい。この超兵器は、試験運用中のものを含めても3隻しかジオンにはなかった。それを投入するというのである。ドロスは、誰が考えても掛け値なしの超兵器だった。
- このアンバランスな、部隊の移動が何を意味するのか?ハリソンには、皆目見当がつかなかった。
-
- その頃484大隊の兵士達のうち下士官以下の若い兵士達、シュタイナー少尉は士官だったけれど、は食堂に集まっていた。
- その表情は一様に明るいものではない。しかし、だからといって絶望に沈んでいるわけでもなかった。彼らは、彼らなりに妥協点を見つけだしていたせいだ。
- 「わたしは、ラル大尉の敵を討つわ」
- 最初に口を開いてそのきっかけを作ったのは、チュリル伍長だった。普段なら、同じ小隊のナカイ伍長あたりがすぐにでも茶々を入れそうなセリフだったが、この日は、誰もそうしなかった。そうしなかったのはその後に続いたこのセリフのせいだったかも知れない。「何かのために戦うんでしょ?みんな?」
- 暗く沈んでいた484大隊の若い兵士達は、あっけにとられたように顔をチュリルの方に向けた。顔には連邦軍が来たら戦わなければならない、という重圧に押しつぶされかかった表情が、ほとんどみんなに浮かんでいた。「意味もなくただ戦うんじゃないわよね?」畳み掛けるようにチュリルはいった。
- しかし、すぐには誰も何も言わなかった。その発想は、連邦軍と戦わなければならないというように思っていた若い兵士達の胸に響いた。
- 「ぼくは、地球から宇宙に対して圧政をひこうとする連邦政府を許せません、だから戦います」
- しばらくしていったのは、シュタイナー少尉だった。相変わらず丁寧な言葉使いと、ギレンの考え方を代弁するようなものいいにあきれたような顔をするものもいたけれど、この場での一番の上官だったので、表向きは誰も反論しなかった。サイクス曹長だけは、大きく頷いた。彼も、どちらかといえばギレンかぶれなのだ。
- 「ぼ、ぼくは、両親と姉弟を守ります」
- 普段は、無口なリー曹長は、そういった。リー曹長は、普段から家族に送る手紙を欠かしたことのない男だった。何人かが、それにはうなずいた。
- 「守るものがあるんでしょ?じゃあ、こんなところでこんな暗い顔をしてても仕方ないじゃん」
- チュリルは、自分の言葉に半分酔っているようだった。ラル大尉のことをいって初めてばかにされなかったことも気分を良くさせていた。「軍曹は?何のために戦いますか?」
- 不意に振られてケイオス軍曹は、一瞬困ったような顔をしたが、すぐに応えた。
- 「女のために戦う」
- 少しばかり生々しい言葉にチュリル伍長は、ぎょっとした。軍の組織の中でそういった表現を聞くとは思ってみなかったせいだ。それに、いかにも醜男という表現が似合いそうなケイオス軍曹の口からそんな言葉がでたせいでもある。
- そんな思いが、チュリルだけでなくみんなの顔に出ていたせいだろう軍曹は、おもむろに胸ポケットから手帳をとりだすと軍曹と同じ年頃の女性とツーショットで写っている写真を見せた。
- そこに写っていたのは軍曹にはもったいないとも思える綺麗な女性だった。美女と野獣、そんな言葉がぴったりだった。
- チュリルなどは、口にこそ出さなかったが、この人はいったい軍曹のどこが好きなんだろう?と真剣に悩んだくらいだ。
- 「ロマノバってんだ。おれは、コイツのために戦う、ジオンのためでもギレン閣下のためでもなくな」
- 微かにシュタイナー少尉が顔をしかめたが、ケイオス軍曹は気に留めなかった。
- 「わたしも、そうです」
- ドペ曹長は、手を上げていった。手を上げる必要は全くなかったのだけれど、学生の時の癖がついでたのだろう。他にも何人かがつられて手を上げた。普段粗野で下品なケイオス軍曹のいったことが一番みんなの共感を誘ったのはチュリルには意外だったのだけれど、考えてみれば彼らの年頃であればもっとも相応しい理由だとも言えた。
- こうしてチュリル伍長が言った一言から、484大隊の兵士達は、少なくとも自分が何のために戦うのか?ということをしっかりと心に刻んだ。
- 確かに、間もなくやって来るであろう連邦軍と戦うことは恐怖以外の何物でもなかったが、それを恐れて逃げ出してしまうわけにはいかないのだ。それはそのまま自分の信じるものや守るべきものを失ってしまうことになるからだった。
- もちろん、それは確固たるものではなかったけれど、ハリソン中尉やブラドー中尉が心配するほどには、少なくとも484大隊の若い兵士達に限っては、チュリル伍長のおかげで士気は低下しなかったのだ。
12月19日 ア・バオア・クー
-
- この日、グラナダから有名なエースパイロット、テリブルピンクで呼ばれるサクラ少尉がやって来ると聞き付けてサクラ少尉が通るルートまで調べてきたのは、サイクス曹長だった。そのエースパイロットが、ただのパイロットなら484大隊の手すきの兵士が全員で見に来ることはなかったに違いないが「何でも、すごい美人らしいですよ」という、サイクス曹長の一言が、ブラドー中尉をも巻き込んでレストルームに集合させることになったのだ。
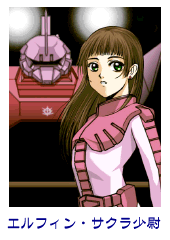 ジオン軍は、ある程度の功績を挙げたパイロットには機体を自由に塗装することを許していた。シャア・アズナブル大佐の赤い機体や、ランバ・ラル大尉の蒼い機体などはジオン、連邦を問わずに有名になっている。しかし、ピンクに塗色しているのは、ジオン軍の数多のモビルスーツパイロットの中でも彼女以外にはなかった。 ジオン軍は、ある程度の功績を挙げたパイロットには機体を自由に塗装することを許していた。シャア・アズナブル大佐の赤い機体や、ランバ・ラル大尉の蒼い機体などはジオン、連邦を問わずに有名になっている。しかし、ピンクに塗色しているのは、ジオン軍の数多のモビルスーツパイロットの中でも彼女以外にはなかった。- 機体を別塗装にするのは、同型機の機体の中から指揮官機を判別させるのを容易にする、という意味もあって特別不用なことではない。
- しかし、色を塗っているからといって全てのパイロットが有名になれるわけではない。その中にあってサクラ少尉は、女性パイロットでかつ、金的持ちであるということが有名にしていた。
- レストルームから見える連絡通路に現れた若い女性少尉を見たとき、あらかじめある程度の知識を得ていたにもかかわらず、484大隊の若い兵士たちは、あっけにとられた。
- 「あれがそうですか?」
- ブレン曹長の言った言葉は、ほとんど全員の感想を代弁しているといっていい。テリブル・ピンクの渾名で連邦軍に恐れられている少尉は、その言葉が表すイメージとは裏腹にあまりにも可憐でありすぎたからだ。ノーマルスーツが似合わないのではない。ノーマルスーツでさえ似合っているのだ。
- 「もっとごっついかと思ってましたよ」
- 「美人ですね・・・」
- 「ちっちゃいですね」
- 口々に484大隊の学徒兵達は、声を潜めながらも、サクラ少尉についての感想を言った。
- ほとんど漆黒の髪は、光線の加減で時折、濃いブラウンの輝きを見せ、その髪が肩の少し下までまっすぐ伸びているのは、少尉の芯の強さも表しているのかもしれない。映画のスクリーンや、テレビに出ていても可笑しくない華やかさが少尉にはあった。そのどちらかというと華奢ですらある少尉が、巡洋艦とはいえ、艦艇を2隻も撃破しているのをすぐに信じろというのは少し難しかった。そして、アジア系の多くがそうであるように、少尉も実際の年齢よりもずっと若く見えるのだ。ハイ・スクールの生徒だ、と聞かされても納得してしまうほどであった。実際の年齢は、20歳の後半なのだけれど。
- 後ろに引き連れている同じ部隊の2人のパイロットが、SPか何かのように見える。いや実際には、そういった役割を自任しているのかも知れない。またそうであっても不自然さは全くなかった。
- そのサクラ少尉が、ア・バオア・クーに立ち寄ったのは、ソロモン方面に対する強行偵察をグラナダとア・バオア・クーの双方で分担するためで、グラナダ側の抽出部隊の一員として、ア・バオア・クーに派遣されて来たのだ。
- 484大隊には、そう言った任務は、まったく関係のないことだったが、少なくとも、むこう何日かは、ほとんどが学生あがりか、それと変わらない若い兵士で占められる大隊の中でサクラ少尉が話題の中心になるには違いなかった。それほど、テリブル・ピンクのサクラ少尉は、少尉自身が意識をするしないにかかわらず鮮烈な印象を見るものに与えた。
- サクラ少尉が、通路を歩いて、反対の扉に消えるまでの時間は、ほんの一瞬でしかなかったけれど484大隊の若い兵士たちに与えた影響は決して時間と比例するものではなかった。
-
- 「別にどうってことないじゃない・・・」
- ただ一人だけ面白くないのはチュリル伍長だった。階級でも負けていたし、経歴でも負けている。おまけに容姿までも、もっともこの点はチュリル伍長にいわせれば、どうってことない、なのだけれど。
- 「おや?御機嫌斜めのようですな?伍長殿?」
- チュリル伍長が、ぼやくのを目敏く聞き付けたサイクス曹長が、からかうようにいった。
- 「当たり前です、みんなしてあんな若い少尉にでれでれしちゃって」
- 「若いってったって、チュリル伍長殿よりは、年上でありますが?」
-
同じようにドペ曹長が、からかった。
- 「それに、どうひいき目に見ても伍長殿より、容姿端麗に見えましたが、わたしの目が悪いのでありましょうか?」
-
追い撃ちをかけるように、ケイオス軍曹が、御丁寧にも敬礼までしていった。
-
いよいよ面白くないのは、チュリル伍長だ。
- 「あたしだって、こんな標準のノーマルスーツじゃなくってああいうのを着れば少しはましにみえますっ!!」
- 士官用に特別にあつらえられたノーマルスーツは、サイズも特注であり、ぴったりとフィットするのだ。しかし、一般兵士用のノーマルスーツや軍服は支給品であり、サイズは大体合わせてあるだけであり、ぴったりフィットするというわけにはいかない。
- 「まあ、お胸は少尉殿といい勝負だわな」
-
ドペ曹長が、チュリル伍長の一番気にしていることを言ったものだから、もう止まらない。
- 「何よ、みんなだってラル大尉に比べたらガキじゃないっ!!」
- 「おいおい、また始まった。チュリルのラル大尉好きには参っちゃうぜ」
- 「なによ・・・」
-
いつもの484大隊のリクリエーションが始まりかけたけれど、大隊の宿舎ではないこともあって、さすがに一緒に来ていたブラドー中尉が止めた。
- 「止さないか、貴様らは全く。いつになったら学生気分が抜けるんだ?」
-
いつもは大目に見ているのだ。よほど揉めないかぎりこの手のリクリエーションは、大抵この年頃の兵士達にとってはいい気分転換になるからだ。しかし、それでも最低限の場所は選ばなければならない。484大隊の宿舎なら問題はないが、ここはレストルームであり、他の部隊の兵士達も出入りが自由なのだ。
- 実際に、何人かの兵士が今から起ころうとすることに期待して顔をこちらに向けている。
- 「ガトルとジッコの隊員は、機体の整備、ザクのパイロットはシュミレーションを3時間だ、ほらっ、休憩はおしまいだ、急げっ」
-
中尉が、それぞれにやるべきことを言い付けると若い兵士達は、多かれ少なかれ不服そうな顔をしながらも、従った。一番不服そうで不満そうなのはチュリル伍長だったけれど、中尉は、それには気が付かない振りをした。
-
- 「・・・というわけなんですよ」
- 昼間の出来事を、士官室横のカンファレンスルームでくつろぎながらブラドー中尉が、話を少しばかりおもしろ可笑しくしながらハリソン中尉に話して聞かせていた。ハリソン中尉とブラドー中尉のほかには、同じ大隊の兵士はいなかったが、2人だけというわけではなかった。「なんていうか、思ったほど彼奴等はびびってませんよ」
- グラナダのエースがやってくるというのを聞き付けて、見に行こうと言い出したのも彼らの中の1人だったらしい。それは、心に余裕があることの証明のようなものだった。
- 「どういう風の吹き回しなんだか?」
- 学徒兵達が、ハリソンが危惧しているほどには委縮していないことを聞かされてハリソンは、少しは気分が楽になった。戦意をなくしている兵士達を率いていかなくっても良いということだからだ。
- 「わざわざ見に行くとは、中尉もよほど暇を持て余していたと見える」
- 「それは言わんで下さい」
- ブラドー中尉は、苦笑いをしながらいった。確かに、中尉の立場の人間のすることではないからだ。「まあ、彼奴等の監督をしてたということにしておいて下さい」
- 「で、そんなにその少尉は美人なのか?」
- 「はあ、やり手のパイロットだと聞いていたのでもうちょっとあれかと思ってましたが、何か不思議な少女の様というか・・・まあとにかくあれはいい女です」
- 「惚れたんじゃないだろうな?」
- うっすらと目を閉じて思い浮かべながら話をするブラドー中尉に、笑いながらハリソン中尉は言った。
- 「まさか、冗談は止して下さいよ」ブラドー中尉は少し慌てたように言った。「しかし、いい女です。あれで金的持ちなんですからね、少しばかり驚いちゃいますよ。まあ、いい女という1点で見ればどこかの補給士官には敵いませんけどね」
- やられっぱなしというわけにはいきませんよ、という顔をしてブラドー中尉は少しばかりやり返した。
- 「まあ、そりゃあそうだ」
- しかし、悪びれもせずにそれを全くそのまま受けられては、ブラドー中尉の負けだった。
- 「全く、中尉には謙遜ってもんがないんだから困りますよ」
- ブラドー中尉は、最後にそういうと、またハリソン中尉のリンダ少尉自慢が始まらないうちに退散することに決めて、腰を上げた。
|