- 12月19日 コンペイトウ
-
- 「ローレン・ゲリン少尉です」
- ソロモン、現在ではコンペイトウ、を出航するにあたって新たに54戦隊は、ジム16機、ボール32機を受領した。もちろん、各艦の中に収納できるわけもなく、艦外係留してのことだ。同時に、これ以降哨戒任務中には、新たなモビルスーツの受領はないことも表わしている。
- 各艦に4機のジムと8機のボールが割り振られ艦外に係留されたのだ。
- その新しく乗り込んできたパイロットにゲリンは、自己紹介をかねて名乗った。
- 「ほう、少尉が?」
- 新しいジム4機のパイロットの隊長らしい男が、ゲリンをしげしげと見ながら言った。何か、予備知識を持っているらしい、それも良くない意味でだ。
- 「何か?」
- 「べ〜つにぃ、空軍上がりの女隊長がいるって聞いてたもんでね。それが、同じ艦になるとは思ってなかっただけさ」
- 名乗りもしないこのふてぶてしい面構えの少尉は、階級章は同じだが、軍隊勤めは長いようだった。後ろでは、同じように一癖も二癖もありそうな3人のパイロットが、ニヤニヤしている。
- 「名前ぐらい名乗ったらどうですか?」
- にやついている少尉にゲリンは、多少きつい言い方でいった。これでは、どちらが新参者か分からない。
- 「おい、名乗れだってよ」
- 3人のうちの一番小柄で太っている軍曹が、他の2人を見ていった。
- 「やめろ、少尉さんに向かって。わきまえんか」
- 少尉は、そういいながらもそれを悪いことだと思っているそぶりは微塵もなかった。「連邦陸軍少尉、フクタだ、こいつらは、ポプキン軍曹、ディーン軍曹、カナベル軍曹だ」
- 名前を呼ばれた順に一応の敬礼を面倒くさそうに3人の軍曹はした。
- どうやらもとは61式戦車乗りで、いまだにそれを引きずっている輩のようだった。合点がいった。だから、空軍上がりという言い方をしたのだ。モビルスーツパイロットになったのにいまだに陸軍ということにこだわっているあたりが、この少尉の根性を伺わせる。モビルスーツパイロットに選抜された以上、腕はおそらく確かなのだろう。あるいは、ていのいい厄介払いだったのかもしれないけれど。
- あまりに癖のあるジムのパイロットと対照的なのは、ボールのパイロット達だった。
- 「ボール隊のオードリー曹長です」
- 控えめというよりは、覇気がないといったほうがいいかもしれない。それが何に起因しているのかは、はっきり言えば明らかだった。生還率が、決して高いとはいえないボールのパイロットだからだ。誰だって、ボールに搭乗して最終決戦に行けといわれれば泣き言の一つもいいたくなるだろう。
- 他の7人のボールパイロットが順に名乗るのを聞きながらゲリン少尉は、自分が、すでにボールパイロットたちを哀れんでいることに気がついた。
- 「で?少尉の仲間たちは?」
- フクタ少尉が、ゲリンの後ろに並んでいる准尉たちをめねつけながら言った。おそらく自分の部下たちが軍曹なのに、はるかに若い彼らが准尉なのが気に食わないのだろう。
- 「ナガレ准尉、タカスギ准尉、コーンウェル准尉です」
- 准尉達の名前を、教えながらもゲリン少尉は、後ろをあえて振り返らなかったが3人が、この古参のパイロット達に気圧されているのが気配で十分に分かった。
- 「ふん、お若いのに准尉たあ、結構なことだ」
- フクタ少尉は、何が何でも気に入らないようだ。
- 時間取れば取るほど、この顔合わせの意味が違ったものになっていくのを感じたゲリンは、多少強引であっても切り上げることにした。今ならまだ、決定的な亀裂をお互いに感じずにすむ。
- 「モビルスーツの整備がありますので失礼します。わたしたちはソロモン戦でジムを出撃させていますので」
- 「ふん、せいぜいいじりすぎて壊さんようにな」
- ゲリンの背中に、フクタ少尉のいやみが飛ぶ、3人の准尉たちはどうしていいのかわからずにただおどおどしているだけだった。まるで先生に引率されている小学生のようなものだ、頼りないにもほどがある。こんなときは、味方になって何か一言くらい言い返してくれてもよさそうなものなのにと思いながらも、また別なところでは、彼らがそんなことができるには若すぎることもゲリンは、理解していた。
- 全く、これで協同戦線が張れるのだろうか?一抹の不安を感じたゲリン少尉は、艦長に小隊単位で別々な任務を与えてくれるよう意見具申することにした。
- 出撃前の顔合わせがなんの成果も生み出さなかったことに落胆しながらも、ゲリン少尉は、今は自分の小隊をベストの状態に持っていくことだけを考えることにした。それには、まずこの場を去ることだ。残されたボール隊員に、フクタ少尉の矛先が向けられることは十分すぎるほど分かってはいたが、だからといってゲリンにはそれをどうすることもできなかった。部隊管轄も違えば指揮系統も違うし、上官でもないからだ。
-
-
12月22日 暗礁空域
-
- コンペイトウからア・バオア・クーへと向かう宙域に広がる暗礁空域、ここは、コンペイトウから月、ア・バオア・クーのどちらへ進攻するにしろ、重要な空域だった。そうである以上、双方の前衛隊が、そこここで小競り合いを繰り広げることになったのは必然である。今しも、2つの部隊が接触し、戦闘を繰り広げようとしていた。深淵なる宇宙では、矮小な出来事のたった一つでしかなかったが、実際に直面している兵士たちにとっては、それは、間違いなく生死を賭けた一大事である。
- ソロモン戦以降の戦闘の多くがそうであったように、ここでもジオン軍は、連邦軍の物量の前に、苦戦を強いられようとしていた。ジオン軍が投入できたモビルスーツが総計14機にしか過ぎなかったのに対し、これは決して少ない数ではない、連邦軍は、艦隊直衛用を除いてなお40機近く、たとえRBL―79を多数含んでいるにしろ、投入することができたのである。
-
- 「3機目は、・・・」
- クレッチッマー少尉は、自分の愛機、RBLー79e管制型ボールの威力を目の当たりにして、驚きを隠せなかった。
- 単機の射撃では満足な戦果を上げられないボールも、このRBLー79eの管制射撃による面の制圧によって大きな成果を挙げつつあるのだ。
- 中隊単位、現在の20機なら能力の半分も必要ない、で管制できるこの管制型ボールによって既に、2機のリック・ドムを撃破していたが、新たに目標に選んだ新型機は、リック・ドムと同じようにはいかなかった。
- RBLー79eのデータでは追い付かない程の機動をみせているのだ。3度の斉射をことごとく躱したどころか、たったの2撃で2機のボールを撃破していた。しかし、3度の斉射によってデータは収集されつつある。
-
- 「うかつな・・・」
- サクラ少尉は、暗礁空域に散在する遮蔽物を巧みに利用して展開する連邦軍の出来損ないに不用意に接近を図った2機のドムが、相次いで撃墜されるのを見て詰った。最も、彼らは、その代償を既にかけがえのないもので支払ってはいたのだけれど。
- 明らかに、20機近い出来損ないは、管制射撃を行っているのだ。それに気が付かずに、ましてや出来損ないだと侮って接近したのでは命がいくつあっても足りはしない。
- サクラ少尉は、危険な出来損ないのフォーメーションを崩すために、ビームライフルの一撃を2度送り込んだ。出来損ない達が動揺するのは手に取るように分かったが、管制射撃は、全く崩れる気配はなかった。ミノフスキー粒子が、戦闘濃度で散布されている以上、母艦から管制されているはずはないのにである。
- 何かが、違う。
- 2機目を撃破した瞬間、感じ取ったサクラ少尉は、メインモニターをスキャンした。出来損ないが、次々にモニター上にプロットされていく。近づいてくる管制射撃を避けながらサクラ少尉は、モニターの中の違いを瞬時に読み取った。
- 読み取った次の瞬間には、サクラ少尉は、ビームライフルの発射ボタンに触れていた。
-
- 次の射撃で、あのふざけたピンク色の新型機を落とせるとクレッチッマー少尉が、踏んだ瞬間、ボール隊にとっての破局は、訪れた。レーザー通信で、新しい解析値を転送しようとした瞬間、クレッチマー少尉の意識は、ぷつりとそして永遠に途切れた。
-
- 出来損ないが布陣するさらにその後方に、それはいた。
- 出来損ないには違いないが、明らかに戦闘用のそれとは異なるそれを、最大望遠で捕らえた瞬間、間髪を入れずにサクラ少尉は、ビームライフルの一撃を送ったのだ。
- 途端に、管制射撃の嵐は途切れた。射撃は続いてはいたが、もはやそれは高速機動するモビルスーツにとってはほとんど脅威にならい散発的なものでしかなかった。
- 後続のモビルスーツが、サクラ少尉の切り開いた活路を無駄にしまいと突入をはかる。3機のザクだが管制射撃のできなくなった出来損ないなど、ザクにでも始末のつく代物でしかなく、あっというまに、殲滅できるはずだった。
- しかし、そうはならなかった。新たな敵、連邦軍の人型が出てきたからだ。
-
- 「ブラックキャッツ、ジム各機、ボール隊を援護しろ!!」
- ゲリン少尉は、崩壊しつつあるボール隊の救援を指揮下の各機に命令した。命令しつつ、ボール隊を蹂躙しようとする敵モビルスーツ隊に、ビームの牽制を入れるのを忘れはしなかった。
- ボール隊が、崩壊しつつあるのは、本来援護すべきイェン小隊のジムが、スカート付きとの戦闘に忙殺されてしまったせいだ。イェン少尉は、無能ではなかったがスカート付きとの戦闘、いやモビルスーツ戦が初めてなのだ、責めることはできない。その崩壊しつつあるボール隊を援護することも大切だったが、この戦場にあって最も危険な敵、管制型を含めて3機のボールを瞬く間に撃破した新型機をどうにかしなければならない。そして、それができるのは自分しかいないはずだと、ゲリン少尉は、自分に言い聞かせた。
- ボール隊には悪いけれど、もう4、5機の被害は、覚悟してもらわなければならない。それでも、援護に駆け付けなければ全滅の可能性すらあったのだから、良しとしてもらわなければならない。
- 「06了解!」
- 「07了解」
- 「08了解!!」
- 不明瞭ながら、指揮下の各機が返答を寄越してきた。反応が、気持ち遅れるが、それは仕方がなかった。ゲリン少尉にいわせれば3人とも、素人なのだから。
- それでも、ジオン軍のモビルスーツ、ザク、は、素人とはいってもより脅威度の高いほうジムの方を対処せざるをえなくなるはずだった。それでボール隊は、全滅の危機から開放されるのだ。しかし、代りに3人の新米パイロットが、命の危機に直面する。けれどボールでザクと交戦することを考えればよほどその生存性は高いのだ。少なくともジムは、ザクのマシンガンの一撃で撃破されてしまったりすることはないし、ザク以上の運動性を持ち合わせているのだから。
- ジムの機体をロールさせると、ゲリン少尉は、相対しつつあるピンクの機体を睨み付け、ジムカスタムを最大戦速で加速させた。そのピンクの機体に意識を集中させながらも、最後に、3人の新兵達の無事をそっと祈るのをゲリンは、忘れなかった。誰が生き残れるのか?それは、誰にも分からないことだったけれど。
-
- 「ちっ」
- サクラ少尉は、たった3回の射撃で故障してしまったビームライフルを投げ捨てながら、まだまだ完成したとはいえない機体を正式化した軍に対して怒りを覚えずにはいられなかった。故障さえしていなければもう4、5機は出来損ないとはいえ撃墜マークを増やせたのだから。
- けれど、戦線を離脱しようなどとは、思いもしていない。障害物のない場所ならともかく、この暗礁空域であれば、浮遊物を巧みに使えば、接敵は容易だからだ。それに、出来損ないを殺戮する機会を奪った連邦軍の人型に礼の一つもしなければ納まらないというものだ。
- しかも、1機がこの自分に敵意をむき出しにして迫りつつあるのだ。自分に向かってきたという失敗を悟らせてあげなければ、そう思うサクラ少尉だった。撃墜マークに連邦軍の人型を加えるのも悪くない、サクラ少尉は、そう思うと、ゲルググに残された武器、ビームなぎなたを抜いた。もろ刃にもなるし、通常のサーベルにもなる近接戦闘用のビーム兵器だ。これも、信頼性は高いとはいえない武器だが、ないよりはましだった。
- 実戦配備されたばかりの機体などこの新型のゲルググにかかれば、どれほどのこともない、サクラ少尉は、そう断じていた。
- しかし、サクラ少尉は、自分が初めて連邦軍の人型と対戦するのだということを失念していた。
-
- 「ふざけてるの?」
- ライフルを投げ捨てたのを見て取って、ゲリン少尉は、怒りを禁じえなかった。けれど、自分の射撃を2度3度と巧みな機動で避ける新型機の機動を見て、怒りを感じている余裕はすぐに無くなった。ゲリンの射撃は、決して不正確なわけではない、それを全く無駄のない機動で避けて見せるピンクの機体にわずかな恐怖を感じ始めた。しかし、だからといって戦意を殺がれたりするようなゲリンではなかった。
-
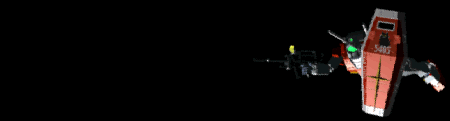
- 命中弾を得られないのは、もちろん、暗礁空域特有の障害物の多さも一因ではある。しかし、それ以上の何かが、ピンクの機体にはある、そう気迫のようなものが装甲越しに感じられるのだ。その無遠慮に叩き付けられる感覚は、まるでゲリンをレイプするかのようだった。そのことが、いやがうえにもゲリンのピンクの機体に対する敵意を煽った。
- ゲリン少尉は、接近してくる新型機にさらに怒りを込めた2撃を加えた。1撃目は、相手をかすめたが、2撃目は、相手が飛び込んだ石っころ、とはいっても長径が100メートルはある、を直撃した。
- その瞬間、盛大な爆発が石っころの表面で起こった。
-
- 気の抜けない相手、それが接敵を開始したサクラ少尉が、相手に対して感じた正直な感想だった。自分でなければ墜されていたかも知れない。ゲルググのビームライフルに比べると、その発射速度は速くないビーム兵器にしてそうなのだ。暗礁空域でなければ、とも思う。
- それほど危険な相手だった。
- 目前の岩の影に飛び込む直前の一撃は、サイドモニターに、減光がかかるほど近くを走り抜けた。
- 白兵戦は、無理かもしれない。そう思ったときだった。飛び込んだ岩石に勢いでビームを放ってしまったのだろう、岩石が飛び散る気配があった。間髪を入れず、サクラ少尉は、ゲルググを機動させた。チャンスは、1度きりのはずだった。
-
- 石っころからは、全方位に渡って破片が飛び散っていく。ビームの高エネルギーを受けて急激に岩石が気化することは爆発と同じ作用だった。ジムの、高性能すぎるセンサーは、飛び散っていく破片の一つ一つについてパイロットに情報を与えようとした。後年のセンサーは、そういった不要な情報をカットすることができたが、初めて実用化された連邦軍のモビルスーツのジムには、まだそういったノウハウがなかった。
- メインモニターに表示される情報の渦の中から必要な情報を見つけたときには遅かった。
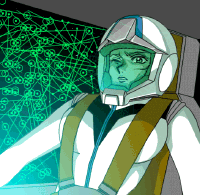
- 「し、しまった・・・」
- 下から急激に接近してくる新型機に気が付き、ライフルを照準しようとしたときには、既に、間合いを詰められていた。体当たりに近い新型機の機動に対し、吹き飛ばされないように、ジムを制動させるのが精いっぱいだった。新型機が照準を付けようとするジムの右腕を、左腕で払う衝撃が伝わってきた。次いで、後方に振り上げた新型機の右腕の先から青白いビームの刃が、ギンッと伸びた。
- ビームサーベルは、連邦軍だけの専売特許です、名前を忘れた技術士官が言っていたはずなのに、と余計な思いが一瞬、脳裏をかすめる。
- 「殺られるものかっ」
- ゲリン少尉は、あきらめてなんかいなかった。
-
- 案の定、飛び散った破片に幻惑されている連邦軍の人型の姿がそこにあった。
 (かわいそうに・・・) (かわいそうに・・・)- 勝利を確信したサクラ少尉の顔に笑みがこぼれる。
- 斜め下方からゲルググを力いっぱいに機動させ、一気に間合いを詰めさせる。その動きに気が付いたのだろう、一瞬ライフルを振り向けようとするのが見て取れたが、その動きが完成する前に、サクラ少尉は、懐に飛び込み連邦の人型の右腕を払った。
- 次いで、ビームなぎなたに、ビームの刃を形成させる、故障も起こさずにビームの刃が形成されたことがモニターに表示される。後は、振り降ろすだけだった。
-

- その瞬間だった。脳裏に「殺られるものかっ」という、女の声が飛び込んできたのは。耳から聞こえたのではない、その声は余りにも鮮明にサクラ少尉に認識できた。
- 「し、しまった」
- 一瞬、その声に動じた瞬間を狙い澄ましたように、機体が激しい衝撃を連続して受け、メインモニターが、ブラックアウトした。その原因が、何なのかを知ろうとするよりも先にサクラ少尉は、ビームなぎなたを一閃させた。それでも、続く衝撃、何かを両断する手応え、何かがぶつかってきた衝撃、鳴り響くアラート。そして、サクラ少尉は、自分がミスを犯したことを死ぬ瞬間に知った。
-
- 「殺られるものかっ」
- 叫ぶと同時に、ゲリン少尉は、ジムの各型に標準装備されている60ミリバルカン砲を発射させていた。同時にジムは、接近してきた敵の驚異を知ってシールドを突き出し、そのまま手を放した。その反動でわずかにジムの機体が沈んだ。
- 放り出されたシールドは、新型機のサーベルによって上下に両断された。そのまま横になぎ払われたサーベルは、ジムの頭部をちょうど人間でいう耳の部分からすっぱりと切り離した。
- まだ残っていた60ミリバルカン砲弾が、誘爆し、一瞬だけメインモニターが、ブラックアウトしたが、間髪を入れずに補助カメラの映像が、目前のバランスを崩した新型機を映し出した。
- その時には、シールドを投げ出した左腕が、ビームサーベルを引き抜いていた。後は、ビームサーベルを一閃させてバランスを崩した新型機の胴に振り降ろすだけでよかった。ゲリン少尉には、新型機が一瞬みせたようなためらいを感じることは何もなかった。
- 「やった・・・」
- 喝采をつぶやくと同時に、誘爆に巻き込まれるのを避けるためにジムを艦隊の方向へ後退させながら、ゲリン少尉は、なぜ、新型機が、一瞬ビームサーベルを振り降ろすのに間をあけたのかを考えた。ほんの一瞬でしかなかったが、明らかにそれは不自然な間であった。それがなければ、両断されていたのは、自分だったはずだ。
- 新型機を撃墜はしたが、ゲリン少尉も、頭部のメインカメラを破壊され、シールドを失った状態では戦闘を続行することは控えめに見ても不可能だった。周囲の警戒を怠らないようにしながら、ゲリン少尉は、ジムを母艦へと帰投させなければならなかった。その時になって、ゲリン少尉は、自分が失禁していることに気が付いて、軽い笑いを漏らした。
- 「こんなことを感じられるのも生きてるおかげよね」
- いかにも自分のイメージとあわないこの事態も、生きていればこそと思えば笑えてくるのだ。それに、誰かに知られることは永遠にないのだ、自分さえ黙っていれば。
- 全周囲を警戒しつつゲリン少尉は、まだ戦闘が続いている空域を不謹慎な笑いを堪えつつ後退した。
- 戦闘は、連邦軍優位のまま終わりつつある。誰が生き残り誰が命を失うのか?それは、帰還してみなければ分からなかった。自分の若い部下達が全員生還してくれることを祈りながら、ゲリンは、自分が生き残れたことに感謝をした。
-
- 戦隊は、結局のところ、ジムの数とビーム兵器に物を言わせてジオン軍の小艦隊を撃破した。10機以上のジオン軍モビルスーツとチベタイプを1、ムサイタイプを2、撃破したのだ。
- 特筆するべきことは、これだけの戦果をモビルスーツ隊だけで上げたということだった。
- もちろん、無傷ではなかった。54戦隊も、艦隊攻撃に振り向けたジムのうち1機を、ジオン軍モビルスーツを迎撃させたうち、ジムが2機、ボールは7機を撃破されていた。さらにジム2、ボール1が、損傷してしまった。しかし、54戦隊本隊には、一指も触れさせることなくこれだけの戦果を挙げたことの意義は高かった。なぜなら、母艦が健在である以上54戦隊は、いまだ十分に作戦行動が継続できたからだ。
|